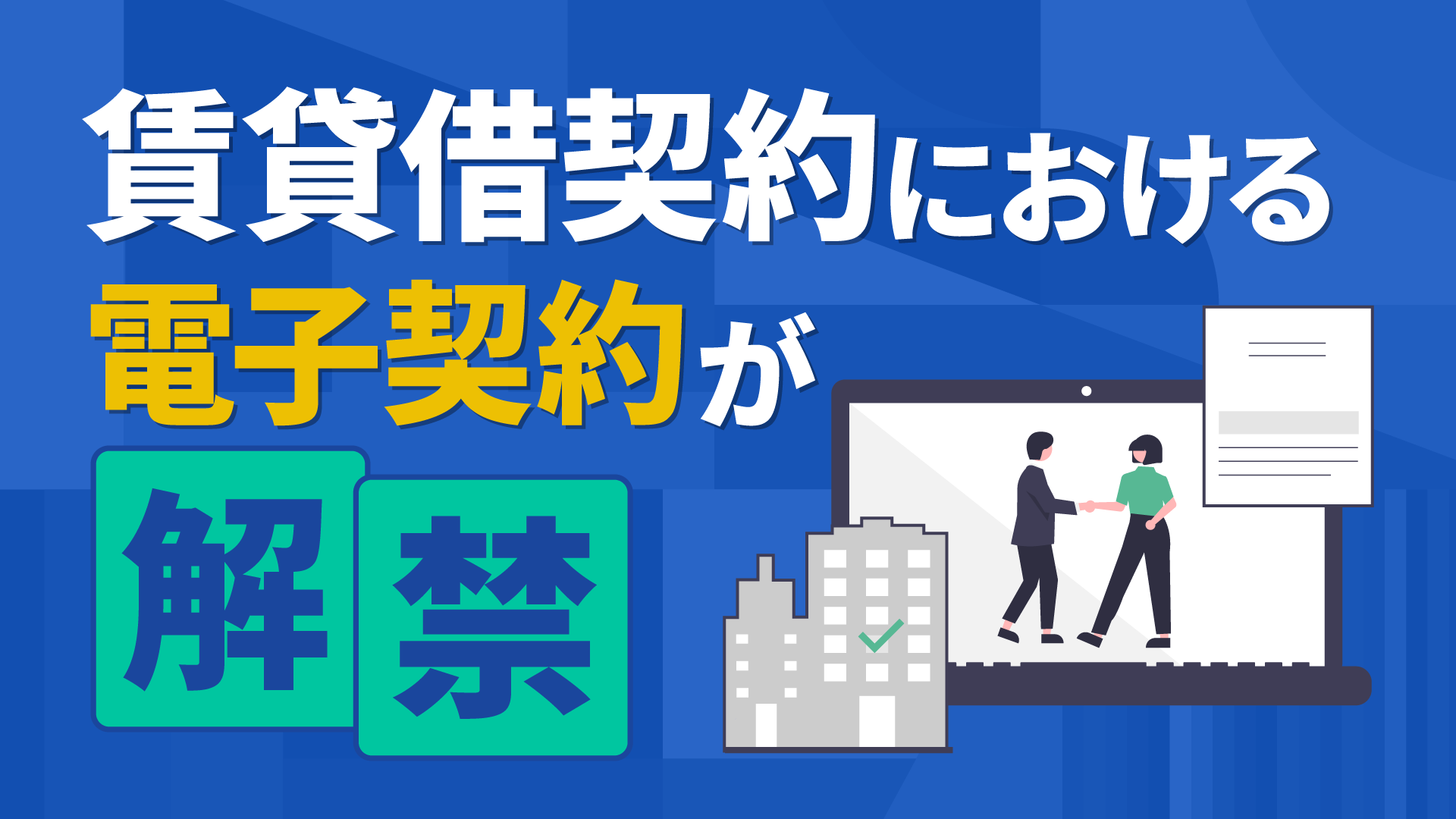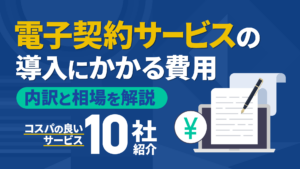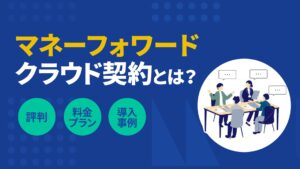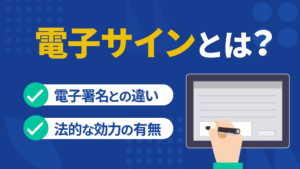2021年以降の法律改正・施行により、不動産の賃貸借契約でも電子契約が解禁となりました。電子契約の導入は、コスト削減や契約日の柔軟な調整など事業者側・入居者側双方にとってメリットがあります。
不動産業界でも導入が進む電子契約ですが「電子契約が可能な書類はどれ?」「賃貸借契約で電子契約を締結する方法は?」といった疑問を抱える企業も少なくありません。
そこで本記事では不動産賃貸で電子契約が解禁された流れをはじめ、電子契約が可能な書類や電子契約の締結方法を解説します。不動産賃貸におすすめの電子契約システムも比較形式で紹介するので、電子契約の導入に迷っている企業はぜひ参考にしてください。
| ・不動産の賃貸借契約を電子化したい ・賃貸借契約に便利な電子契約システムを知りたい ・まずは見積もりを取ってから考えたい 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |
賃貸借契約における電子契約とは

賃貸借契約における電子契約とは、書面ではなくインターネットを通じて手続きを完了させる契約方法のことです。不動産賃貸借契約書や重要事項説明書など、従来は紙媒体で交わされていた書類を電子データで作成し、契約を締結します。
電子契約では、電子署名法に基づく「電子署名」が用いられるのが基本です。電子署名を付与することで、紙の署名と同等の法的効力を持つ契約が成立します。
賃貸物件の契約を電子化すれば、契約書の郵送や印紙税が不要になり、双方の負担を軽減できるのが大きなメリットです。
不動産賃貸で電子契約が全面解禁された流れ

不動産賃貸における電子契約が全面解禁となった背景には、法律の施行や改正が関係しています。
- デジタル改革関連法の成立
- 宅地建物取引業法の改正
- 借地借家の改正
ここからは、賃貸借契約の電子化が加速している理由を法的な観点から見ていきましょう。
デジタル改革関連法の成立
2021年に成立したデジタル改革関連法は、日本社会全体のデジタル化を推進するための包括的な法律です。本法律の施行によって行政手続きや商取引における電子化が進められ、不動産業界にも大きな影響を与えました。
不動産賃貸においては、重要事項説明書への宅地建物取引士の押印が不要になり、電子署名で対応できるようになったのがポイントです。また一部の書類では書面交付の義務も廃止され、重要事項説明書のオンライン交付が可能になりました。
ただし2021年時点では、売買契約や賃貸借契約といった書類の電子化が認められず、完全な電子化はできませんでした。
宅地建物取引業法の改正
不動産賃貸における電子契約が全面解禁となったのは、2022年の宅地建物取引業法の改正以降です。法改正によって、重要事項説明書や賃貸借契約書の電子交付・デジタル署名が認められ、非対面でも賃貸借契約を交わすことが可能になりました。
また、対面が義務付けられていた重要事項説明もオンラインでの実施が許可され、遠隔地にいる取引先や顧客ともスムーズにやり取りできるようになりました。
借地借家の改正
借地借家法は、建物の所有を目的に土地または建物を借りる際に適用される法律です。建物や土地の賃貸借に関する基本ルールを定めており、従来借地借家法では定期借地契約と定期借家契約の電子化が認められていませんでした。
しかし、宅地建物取引業法と同じく借地借家法も改正されたことで、該当書類の電子契約や電子交付が法的に容認されました。電子契約には賃借人の承諾が必要ですが、書面契約に比べて手続きを簡素化できるのは大きなメリットでしょう。
電子契約が可能になった不動産賃貸の書類
2021年以降の法施行や法改正で電子契約が可能になったのは、不動産賃貸借契約書と重要事項説明書の2つです。ここでは、電子契約できる不動産賃貸の書類を詳しく解説します。
不動産賃貸借契約書
不動産賃貸借契約書は、賃貸物件の使用条件や賃料といった必要項目を明記した書類です。宅地建物取引業法では、以下のように不動産賃貸借契約書の交付が義務付けられており、第37条の規定に基づくことから37条書面とも呼ばれています。
| 第五章 業務 第三十七条:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 |
従来37条書面は、宅地建物取引士による記名・押印と書面交付が義務付けられていましたが、2022年の法改正で押印が不要になり、電子交付も認められています。
重要事項説明書
重要事項説明書は、賃貸物件の契約を行う前に、入居希望者に対して物件や契約条件について説明するための書類です。従来は対面かつ紙媒体を用いた説明が義務付けられていましたが、2022年の宅建業法によって電子交付が可能になりました。
重要事項説明自体もオンラインで行えるようになり、パソコンやスマホを利用した重要事項説明はIT重説と呼ばれています。IT重説は遠隔地にいる顧客との契約にも便利ですが、事前に相手方の承諾を得なければいけません。
【事業者側】賃貸物件の電子契約で得られるメリット

賃貸物件の電子契約は、事業者側・入居者側双方にとってメリットがあります。例えば事業者側は契約業務の効率化につながるだけでなく、以下のようなメリットを得られます。
- 印刷代や郵送代といったコストを削減できる
- 潜在顧客の獲得につながる
- 書類保管にかかる手間を省ける
- 賃貸借契約の更新手続きが楽になる
ここではまず事業者側に焦点を当て、賃貸物件の電子契約を進めるメリットを見ていきましょう。
印刷代や郵送代といったコストを削減できる
電子契約を導入すれば、紙媒体の印刷や郵送が不要になるため、大幅なコスト削減が期待できます。特に複数物件を扱う事業者にとって、契約書関連の経費を削減できるのは大きなメリットです。
同時に書類の印刷や封入にかかっていた人件費も削減できるので、長期的な目線で見ても有効な経費削減策といえるでしょう。契約書類の電子化は、コスト削減だけでなく環境負荷の軽減にもつながり、企業のサステナビリティ推進に寄与します。
潜在顧客の獲得につながる
電子契約の導入は、潜在顧客へのアプローチにも有効です。遠方に住む顧客や海外在住者にとって、オンラインで契約手続きが完結することは大きな魅力となります。
電子契約を導入すれば、地理的な制約を超えて物件をアピールできるため、顧客層の拡大に役立つでしょう。契約者のサインや押印も不要なので、迅速な契約締結が可能となり、顧客の満足度向上にも貢献します。
書類保管にかかる手間を省ける
賃貸借契約を書面で交わすと書類の保管場所や整理作業が必要となり、多大な手間とコストがかかります。
その点電子契約なら、契約書を電子データとして管理できるため、物理的な書類保管スペースを必要としません。手作業での仕分けや保管も不要なので、書類の紛失リスクを軽減できるのがメリットです。
また電子契約システムの検索機能を活用すれば、必要な書類を瞬時に見つけ出すことができます。更新手続きや修正が必要な書類もすぐに特定できるので、事務作業の効率化につながるでしょう。
賃貸借契約の更新手続きが楽になる
電子契約を導入すれば、賃貸借契約の更新手続きもオンライン上で完結可能です。契約書の再作成や郵送といった手間が少なくなるので、スピーディーに更新手続きを済ませられます。
また電子契約システムのなかには、更新時に発生する変更事項を自動で反映できるものもあり、手作業によるミスを減らせるのが魅力です。更新のタイミングを通知する機能があれば、更新忘れといった事態も防げるでしょう。
【入居者側】賃貸物件の電子契約で得られるメリット

賃貸物件の電子契約は、入居者側にとってもメリットがあります。
- 契約日を柔軟に調整できる
- 賃貸物件入居までのコストを削減できる
入居者側にとってどのような利点があるか把握しておけば、自社における導入効果も判断しやすくなるでしょう。以下で詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてください。
契約日を柔軟に調整できる
電子契約はオンラインでの手続きとなるため、入居者は契約日の調整がしやすくなります。時間や場所の制約を受けずに手続きできるので、入居者が忙しい場合でも好きなタイミングで契約することが可能です。
特に「早期の入居を希望しているが店舗に出向く時間がない」という入居者にとって、契約日を柔軟に調整できるのは大きなメリットでしょう。
賃貸物件入居までのコストを削減できる
電子契約の導入は、入居者にとってもコスト削減につながります。部屋さえ決めれば、契約手続きで店舗に足を運ばなくて良いので、交通費を節約可能です。
また遠方に住んでいる場合も、移動時間を考慮した日程調整をする必要がなくなります。電子形式でのやり取りが基本なので、金銭的なコストはもちろん、繰り返しの来店による時間的・体力的コストを減らせるのもメリットです。
賃貸借契約で電子契約をする注意点(デメリット)
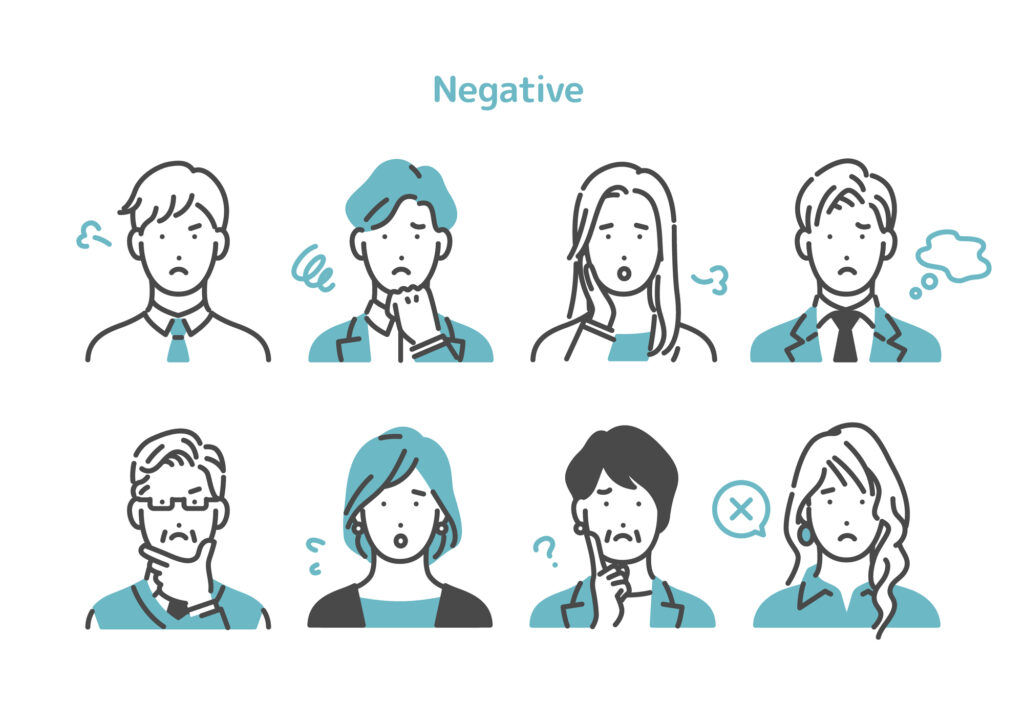
事業者・入居者双方にメリットがある電子契約ですが、導入時にはいくつか注意したいポイントもあります。
- 賃貸物件のオーナーに周知しておく
- 電子署名法に準拠した契約を行う
- 電子帳簿保存法に準拠してデータを保管する
- 必要に応じて業務フローを再構築する
- セキュリティ対策を徹底する
それぞれ詳しく解説するので、事前に注意点やデメリットを把握したうえでトラブルなく電子契約を導入しましょう。
賃貸物件のオーナーに周知しておく
電子契約を活用するためには、賃貸借契約の相手方である入居者やオーナーの同意が必要です。
特にオーナー側は、電子契約の機能や法的有効性に不安を感じる場合もあるので、導入前に丁寧に説明することが求められます。スムーズに電子契約を進めるためには、サポート体制を整えておくことも大切です。
また賃貸物件のオーナーによっては、電子契約の導入に同意を得られない可能性もあります。どのような状況にも柔軟に対応できるよう、電子契約だけでなく書面契約も締結できる体制を整えておくのもひとつの方法です。
電子署名法に準拠した契約を行う
不動産賃貸における電子契約では、電子署名法に準拠しなければいけません。電子署名法は、電子署名が紙の契約書における署名・押印と同等の効力を持つことを定める法律です。
具体的には以下のように定められており、電子署名が付与された電子文書には法的効力があると認められています。
| 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 第三条:電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 |
電子署名は「契約者本人が署名していること」「契約データが改ざんされていないこと」の証明となります。電子契約の証拠力を高めるためにも、電子署名法に準拠したシステムを導入するようにしましょう。
電子帳簿保存法に準拠してデータを保管する
電子契約で締結した契約書類は、電子帳簿保存法に基づいて適切に保管する必要があります。電子帳簿保存法は、国税関連の帳簿や書類の保管要件を定めた法律です。
電子帳簿保存法は何度か改正を繰り返しており、2022年の改正では「電子取引した文書は電子データで保存すること」が義務付けられました。電子帳簿保存法の要件を満たさない場合、税務調査で問題が発生する恐れがあるので注意が必要です。
また電子契約書をはじめとする帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければいけません。監査で求められた場合に提示できるよう、法律に準拠した形で電子契約書を保存しておきましょう。
参考:
国税庁 | 電子帳簿等保存制度特設サイト
国税庁 | No.5930 帳簿書類等の保存期間
必要に応じて業務フローを再構築する
電子契約を導入すると、従来の業務フローの再構築が必要になる場合もあります。適切な業務プロセスを構築しなければ、かえって混乱を招く可能性もあるので注意が必要です。
また契約担当者の業務も変更となるため、社員への教育やマニュアル整備も欠かせません。電子契約の運用に慣れるまでは時間と労力を要するため、導入前に十分な準備期間を設けることが大切です。
セキュリティ対策を徹底する
電子契約にはサイバー攻撃やデータ漏洩のリスクがともなうため、強固なセキュリティ体制を整える必要があります。利用する電子契約サービスが、データ暗号化や不正アクセス防止対策などを実装しているか確認しましょう。
また利用者側でも、多要素認証や強固なパスワードポリシーを導入することが重要です。閲覧権限や承認権限も詳細に設定しておけば、社外への情報漏れを防止できます。
賃貸借契約における電子契約の締結方法

不動産賃貸で電子契約を締結する際は、いくつかのステップを踏む必要があります。大体の流れは書面契約と変わりませんが、注意点があるので事前に確認しておきましょう。
- 契約書類の作成:賃貸借契約書や重要事項説明書を電子形式で作成。法的に適切な形式で作成することが重要
- 重要事項説明(IT重説)の実施:重要事項説明をオンラインで実施。事前にIT重説の実施に同意を得たうえで、ビデオ通話システムを利用して説明
- 電子署名の実行:契約者双方が契約に同意したうえで、電子契約システムを通じて契約書に電子署名を付与(契約の締結)
- 契約書の保管と共有:署名が完了した契約書は、システム内で安全に保管
契約締結後も、更新手続きや解約通知などの管理を電子化することで、業務効率をさらに向上させられます。
【比較表】不動産の賃貸借契約におすすめの電子契約システム
電子契約を導入するなら、電子署名法や電子帳簿保存法に準拠した電子契約システムを利用するのがおすすめです。電子契約システムの大半は電子署名やタイムスタンプを自動で付与できるので、手軽に信頼性の高い電子契約を締結できます。
以下では、不動産の賃貸借契約におすすめの電子契約システムをまとめました。電子契約システム選びに迷っている方はぜひ参考にしてください。
| サービス名 | 利用できる機能 | 特徴 | おすすめの人(企業) | 料金プラン(無料か有料か) | セキュリティ性能 | 電子署名のタイプ(種類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウドサイン | ・メール認証と2段階・2要素認証 ・電子署名、タイムスタンプ付与機能 ・アカウントや権限のカスタマイズ機能 ・書類インポート機能 ・リマインド機能 ・テンプレート設定 ・ステータス確認 | ・ファイルアップロードやマイナンバー認証など認証、締結方法が豊富 ・自社システムのほか、100以上の外部サービスと連携可能 | ・大企業 ・自治体 ・中小企業 ・個人事業主 | ・Light:月額11,000円 ・Corporate:月額30,800円 ・Business:※ ・Enterprise:※ ※各プラン、ユーザー数と送信件数は無制限 ※送信件数ごとの費用は220円(BusinessとEnterpriseプランは要問合せ) ・無料プラン有り(送信件数:月3件まで、ユーザー数:1名まで、 電子署名+タイムスタンプ有り) | ・暗号化通信 ・保存ファイルの暗号化 ・ファイアウォール ・アカウント保護 ・IPアドレス制限 | 立会人型 |
| マネーフォワードクラウド契約 | ・案件管理 ・契約書作成 ・申請、承認のワークフロー機能 ・承認ステータス管理 ・電子署名、タイムスタンプ付与 ・複数契約の同時締結機能 | ・申請や承認の履歴とあわせて契約書を一元管理 ・他社の電子契約サービスから受領する電子契約データも、自動で取り込み可能 ・紙の契約書も管理可能 ・契約書送信料と契約書保管料が無料 | ・個人事業主 ・中小企業 | ・パーソナルミニ:月額1,408円(月額プラン) ・パーソナル:1,848円(月額プラン) ・パーソナルプラス:3,278円(年額プラン) ・スモールビジネス:4,378円(月額プラン) ・ビジネス:6,578円(月額プラン) ※IPO準備・中堅〜上場企業向けプランは要問合せ ※1ヶ月無料トライアル有り ※ | ・通信の暗号化 ・契約締結前に法務担当者とのリーガルチェックのやり取りが可能 ・アクセスキー設定 ・シングルサインオン(SSO)対応 | 立会人型 |
| 電子印鑑GMOサイン | ・スキャン文書管理機能 ・タイムスタンプ付与 ・署名互換機能 ・アクセスコードのSMS送信 ・電子署名機能(実印、契約印、手書きサイン、印影登録なども可能) ・複数文書⼀括送信 ・操作ログ管理 ・文書検索 | ・契約印タイプの送信料が110円/1件と安価 ・権限設定や閲覧制限機能により、重要書類も安全に管理 ・電子署名法に準拠 ・立会人型と当事者型の両方に対応 | ・個人事業主 ・中小企業 ・大企業 ・不動産業界 | ・フリープラン:無料(ユーザー数1名のみ、送信数上限5件/月、署名方法は立会人型のみ対応) ・契約印&実印プラン:月額9,680円(ユーザー数・送信件数ともに無制限、立会人型と当事者型に対応、立会人型の送信料110円/件、当事者型の送信料330円/件) | ・S/MIME ・IPアドレス制限 ・二要素認証 ・クライアント認証 ※一部オプション(セキュリティ・内部統制パック) | 当事者型・立会人型対応のハイブリッド型 |
| BtoBプラットフォーム 契約書 | ・契約書発行 ・電子契約(契約締結) ・押印機能 ・契約書保管(自社保管) ・権限管理 ・API連携機能 | ・進捗状況を細かく確認可能 ・シンプルなUIで操作が簡単 ・取引先は無料会員のまま、多様な機能を利用可能 ・過去に紙でやり取りした文書もクラウド上で保管 ・電子帳簿保存法に対応 | ・小規模事業者 ・中小企業 | ・フリープラン:無料(ユーザー数無制限、電子契約15件/月、電子保管3件/月) ・シルバープラン:11,000円~(ユーザー数無制限、電子契約は通常署名55/通、長期署名 165円/通、電子保管3件/月) ・ゴールドプラン:33,000円(ユーザー数無制限、電子契約は通常署名55/通、長期署名 165円/通、電子保管無制限) ※全プランにおいてワークフロー機能と連携が可能(3ユーザーまで無料) ※ゴールドプランのAPI連携機能には別途設定費用が必要 | ・電子化したデータは、ブロックチェーンに記録 ・通信の暗号化 ・ファイアウォール ・データの暗号化 ・IPS ※セキュリティ強化オプション有り(不正ログイン防止、ID/パスワードの一元管理など) | 当事者型・立会人型対応のハイブリット型 |
電子契約システムによって機能や料金が異なるので、自社で業務効率化したい範囲や予算に応じて選びましょう。
不動産賃貸の電子化には、実績豊富な電子契約システムを導入しよう
本記事では、不動産賃貸における電子契約が解禁された流れのほか、電子契約の締結方法やおすすめの電子契約システムを解説しました。不動産の賃貸借契約を電子化すれば、事業者側だけでなく入居者側にもメリットがあります。
ただし賃貸借契約を電子で交わす際は、電子署名法や電子帳簿保存法といった法律に準拠しなければいけません。電子契約システムを導入すれば、手間をかけずに法的有効性のある電子契約を締結できるので、自社に適したシステムを選びましょう。
| 以下の問題でお悩みの方は、こちらのボタンからぜひお気軽にお問い合わせください。 ・自社に合った電子契約システムを知りたい ・不動産賃貸の電子化に適した電子契約システムが分からない ・導入や運用にかかる費用を知りたい |