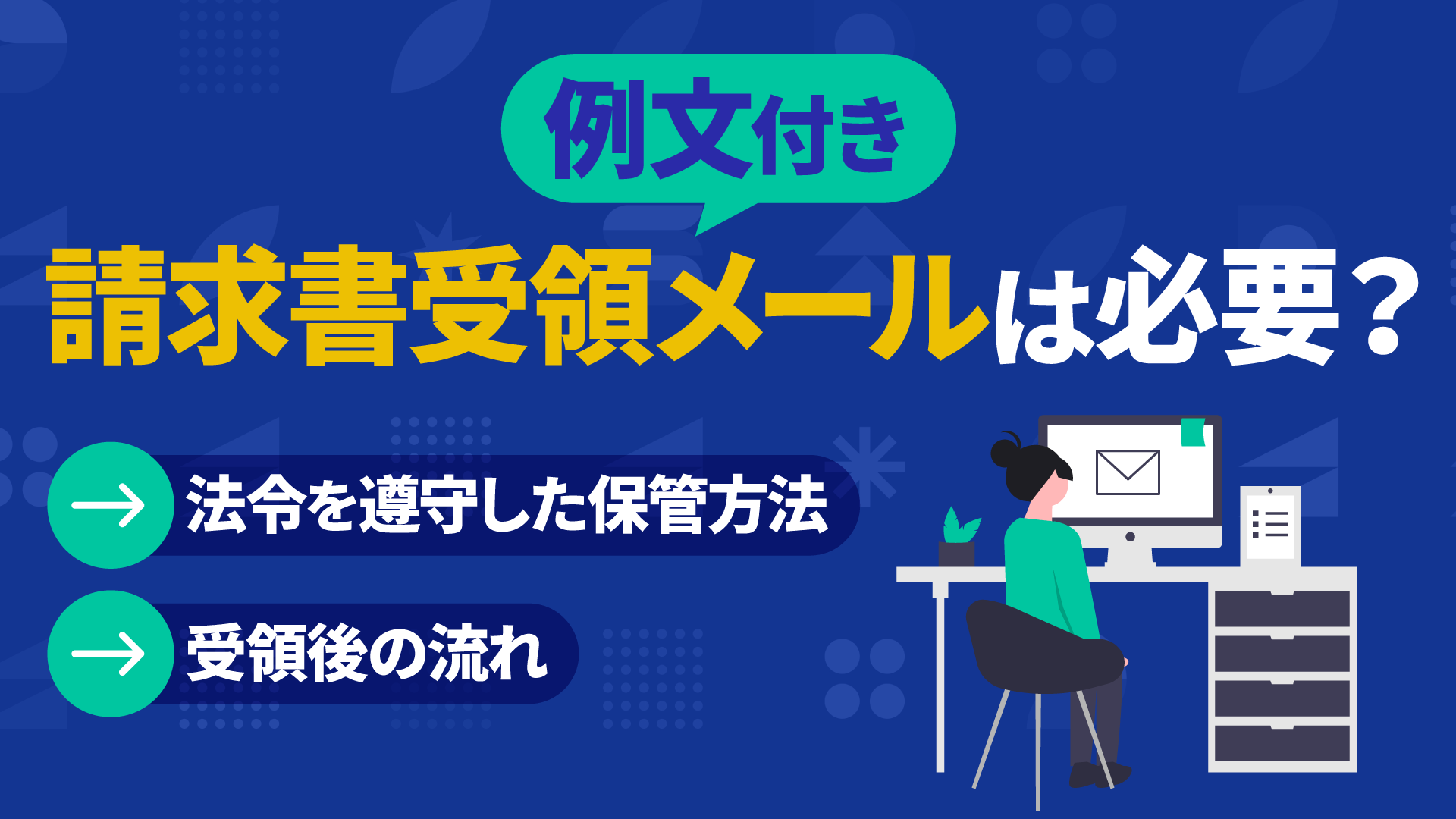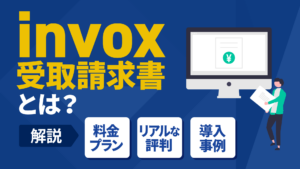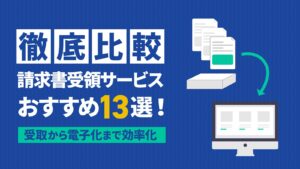請求書を受け取ったら、受領した旨を伝えるメールを送信するのが一般的です。請求書受領メールを送信することで相手に安心感を与えられるだけでなく、データの受け渡しに関するミスやトラブルを未然に防げます。
取引先との信頼構築にも欠かせない請求書受領メールですが、「メールに書くべき内容は?」「メールを書くときのビジネスマナーはある?」などの疑問を抱える企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、請求書受領メールを送信する目的や記載すべき内容をはじめ、法令を遵守した請求書の保管方法や受領後の流れをまとめて解説します。請求書受領メールの例文も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 法令を遵守して請求書を保管したい請求書を受領したあとの業務を効率化したい請求書システムの入れ替えを検討している 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |
請求書の受領メールを送信する目的

請求書の受領メールを送信する目的は、請求書を確実に受け取ったことを取引相手に伝えるためです。受領の連絡をしなければ、送信者は請求書が届いているか確認できず、業務の遅延やトラブルの原因となる可能性があります。
また、請求書の受領メールは、支払い予定日や内容確認の進捗を示すためにも有効です。メールを送付することで取引先は安心して請求書の処理状況を把握でき、のちのちの催促や問い合わせの手間を省けるようになります。
請求書の受領メールを通じて感謝の意を表せば、相手との信頼構築にもつながり、円滑なコミュニケーションに役立つでしょう。
請求書の受領メールに入れる内容

請求書の受領メールには、取引先に対して確実に受領を伝えるための情報を盛り込む必要があります。具体的には、以下のような内容をメールに含めましょう。
| ・請求書を受領した旨 ・感謝の意 ・請求内容(「○月請求分」「○月○日お支払い分請求書」「請求書No.○」など) |
請求書の受領メールでは、受領した請求書の概要と感謝の意を記載するのが一般的です。併せて請求書の発行番号や発行日など請求内容を簡潔に記載しておけば、相手が送信した請求書を特定しやすくなります。
最後に相手に対して感謝の意を伝えることで、より丁寧な印象を与えられるでしょう。必要に応じて今後の流れを記載したり、誤りや不明点がある場合は、早急に連絡をお願いする一文を添えたりするのがポイントです。
【ビジネス向け】請求書の受領メール例文
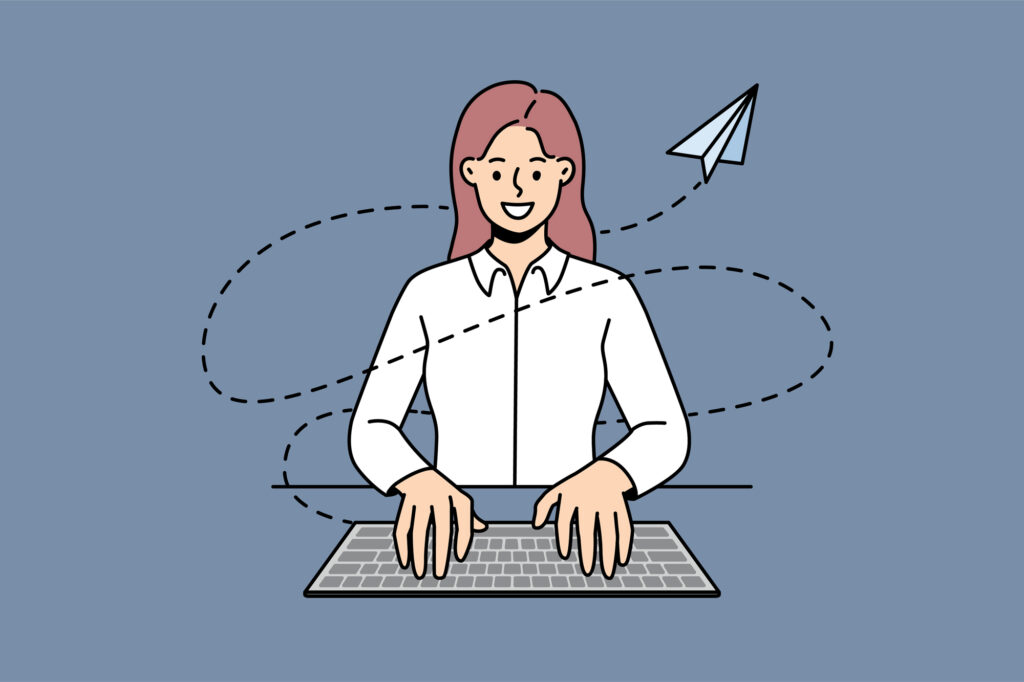
迅速な請求書処理に欠かせない請求書受領メールですが、具体的にどのように書けば良いか迷っている方も多いのではないでしょうか。本章では、請求書の受領メールの例文を以下2パターンに分けて紹介します。
- 通常の請求書の受領メール
- 請求書に番号が付与されている場合の受領メール
受領メールの文章をテンプレート化しておけば、毎回文面を考える必要がないので業務効率化につながるでしょう。ビジネスシーンで請求書受領メールを送る方は、ぜひチェックしてみてください。
通常の請求書の受領メール
通常の請求書の受領メールでは、受け取った請求書の概要やお礼などを簡潔に伝えましょう。
| 件名:請求書受領のご連絡 ○○株式会社 ○○部 ○○様 いつもお世話になっております。○○株式会社の○○です。 本日、○月○日付の請求書を受領いたしました。 迅速にご送付いただき、誠にありがとうございます。 内容を確認のうえ、支払予定日である○月○日までに対応させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 |
会社名や担当者名はもちろん、支払い期日などを明確に記載するのがポイントです。
請求書に番号が付与されている場合の受領メール
やり取りしている請求書が複数ある場合は、各請求書に番号が付与されているのが一般的です。請求書の受領メールを送る場合も、請求内容が分かるよう番号を忘れずに記載しましょう。
| 件名:請求書No.○○○○受領のご連絡○○株式会社 ○○部 ○○様 平素よりお世話になっております。○○株式会社の○○です。 本日、貴社より送付いただいた請求書No.○○○○をたしかに拝受いたしました。 迅速に確認させていただき、支払予定日である○月○日までに手続きを進めてまいります。 何か不備がございましたら、早急にお知らせください。 お忙しい中、迅速なご対応ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
なお、請求書の番号は、本文だけでなくメールの件名にも書くようにしてください。
請求書の受領メールを送信する際のマナー・注意点

請求書の受領メールを送信する際には、取引先に配慮したマナーが求められます。
- 可能な限り早く送信する
- 丁寧な言葉で感謝を伝える
- 「受信」という表現は控える
ここからは、請求書の受領メールを送るときに注意したい3つのポイントを詳しく見ていきましょう。
可能な限り早く送信する
受領メールは、請求書を受け取ったら速やかに送信するのが基本です。受領メールの送信が遅れると、取引先に不安や誤解を与えてしまう可能性があります。
可能な限り早く送信することで、取引先に対して「請求書が確実に届いている」という安心感を与えられるでしょう。また、早急に送信しておけば、万が一内容に誤りがあった場合も速やかに対応できるメリットがあります。
請求書の受領メールは受領後24時間以内、遅くとも翌営業日中に送信するのが理想です。ただし、早朝・深夜や祝日に送信するとマナー違反とみなされる場合もあるので、送信する日時にも気を配りましょう。
丁寧な言葉で感謝を伝える
請求書の受領メールでは、単に請求書の受領を伝えるだけでなく、相手への敬意を示すことが大切です。表現についても「請求書を受け取りました」ではなく「拝受しました」「受領いたしました」など丁寧な言葉を用いると良いでしょう。
また、「ご送付いただき、誠にありがとうございます」や「迅速なご対応に感謝申し上げます」などの言葉を添えることも重要です。感謝の意を相手に伝えることでより誠実な印象を与えられます。
「受信」という表現は控える
請求書の受領メールでは「受信」という表現は避けるようにしましょう。「受信」はメールでよく見られる表現ですが、書類のやり取りで使うのは一般的ではありません。
受信は「通知や信号を受け取る」という意味を持つので、請求書を受け取った際は「受領」や「拝受」が適切な表現になります。「ご送付いただいた請求書をたしかに受領(拝受)いたしました」と表現すれば、よりビジネスライクで礼儀正しい印象を与えられるでしょう。
取引先との信頼関係を深めるためにも、言葉選びには細心の注意を払うことが大切です。
請求書を受領したあとの業務の流れ

請求書を受け取ったら受領メールを送信し、請求処理を行います。必要に応じて捺印したり未払い分を仕分けたりと複数のステップを踏む必要があるので、事前に流れを確認しておきましょう。
- 請求書の受領メールを送信する
- 必要に応じて検印・捺印をする
- 未払い分の請求書をファイルに保管する
- 期日までに支払い処理を済ませる
- 支払い済みファイルに請求書を保管する
請求処理の遅延やミスは、企業の信頼性にも関わります。支払い期限を守るのはもちろん、法令に準拠したうえで正しく請求処理を済ませることが大切です。
1. 請求書の受領メールを送信する
請求書を受け取ったら、最初に受領確認のメールを送信します。請求書の発行番号・金額・発行日など基本情報を記載し、請求書が正しく届いたことを取引先に伝えましょう。
手違いや不明点がある場合は、速やかにその旨を相手に報告するようにしてください。
2. 必要に応じて検印・捺印をする
受領した請求書によっては、社内規定に基づいて検印や捺印を行う必要があります。検印や捺印は、請求書が正当なものであることを証明し、社内で正式な書類として認められるために重要な作業です。
金額・取引内容・期日など請求内容に不備がないか細かく確認し、社内の承認フローにしたがって関係部署や責任者間で回覧しましょう。特に請求金額が大きい場合や複数の部署が関与している場合は、トラブルを防止するためにも慎重にチェックすることが大切です。
3. 未払い分の請求書をファイルに保管する
請求内容を確認したら、支払期日別に未払い分として保管しておきましょう。紙媒体の請求書の場合はファイルやバインダーを活用するのが基本ですが、電子データの場合はデジタルツールを活用するのがおすすめです。
請求書管理システムを使えば支払い状況を一元管理でき、期日通りの支払いがスムーズになります。支払い忘れや二重請求などの事態を防ぐためにも、支払いのスケジュールを明確にしておくことが大切です。
4. 期日までに支払い処理を済ませる
請求処理で大事なのは、支払いを期日までに済ませることです。支払いの遅延は取引先との信頼関係を損なうだけでなく、場合によっては違約金の発生や取引停止につながる可能性もあります。
期日通りの支払い処理を実現するためにも、カレンダーや請求書管理システムで支払い期日を管理しておきましょう。期日が近づいたタイミングでアラートを発するシステムなら、支払い忘れを防ぐことができます。
5. 支払い済みファイルに請求書を保管する
支払いが完了した請求書は、支払い済みのファイルやフォルダに移動させて適切に保管しましょう。「支払い済み」や「入金済み」などのスタンプを押しておけば、二重払いを防止できます。
また、発行日順や取引先ごとに保管しておけば、あとから見返しやすく、会計監査や税務調査でも過去の取引記録をスムーズに参照可能です。電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠した保存が必要なので、事前に保管要件を確認しておいてください。
請求書の送付依頼メールの例文

取引先から請求書が送付されなければ、支払い処理を進められません。期日までに請求書が届いていない場合は取引先が失念しているケースもあるため、以下の例文に沿って請求書送付を依頼するメールを送りましょう。
| 件名:請求書送付のお願い 本文: ○○株式会社 ○○様 いつも大変お世話になっております。 ○○株式会社の○○です。 ○月○日にご依頼した業務に関する請求書の送付について、お願い申し上げます。 お手数をおかけしますが、以下の条件で送付いただけますと幸いです。 請求書送付先:○○株式会社 ○○部 ○○宛 請求金額:○○○円(税込) 支払期日:○月○日 不明点や確認事項がございましたら、どうぞご遠慮なくお知らせください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 |
請求書の催促や送付依頼を送る場合も、相手に不快感を与えないよう丁寧な言葉遣いを心がけてください。請求書の送付先や請求金額を具体的に記載しておけば、取引先もスムーズに対応しやすくなります。
請求書の受領・処理で直面する課題

請求書の受領や処理業務では、以下のようにさまざまな課題に直面する場合があります。
- 取引先によって請求書の形式が異なる
- 手入力によるミスが生じやすい
請求業務の効率性や正確性に影響が生じるリスクもあるため、事前に課題を認識したうえで解決策を考えておきましょう。
取引先によって請求書の形式が異なる
請求書の形式は、紙やデータなど取引先によって異なります。受領方法も以下のように一律ではなく、異なる形式での請求書処理・管理には手間がかかります。
- 紙の書類で郵送
- PDF形式の請求書を電子メールで受領
- システムを介して請求書をダウンロード
支払い完了までの業務が遅くなるだけでなく、取引先によって請求書のテンプレートが異なる場合は金額や請求内容の確認にも時間がかかるでしょう。
上記のような課題を解決するためには、PDFやメールなど幅広い形式の請求書受領に対応できるシステムの導入が有効です。大半の請求書受領システムは、請求書を取り込むだけで自動データ化できるので経理担当者の負担軽減につながります。
手入力によるミスが生じやすい
請求書の情報を手動で入力していると、金額や請求書番号、日付などの項目で入力ミスが発生するリスクがあります。特に大量の請求書を処理する際は、誤って異なる取引先に請求してしまう可能性もゼロではありません。
手入力によるミスを防ぐためには、ダブルチェックの体制を整えたり自動化ツールを導入したりするのがおすすめです。AI技術による請求書認識技術を搭載した請求書受領システムなら、請求書の内容を自動で読み取り、データ入力を自動化できます。手入力による手間を省けるだけでなく、高精度でのデータ入力を叶えられるのがメリットです。
【比較表】請求書管理におすすめのクラウドシステム
請求書の受領や処理で直面しやすい課題を解決したい場合は、請求書管理システムを導入するのがおすすめです。
ここでは、invox受取請求書・BillOne・バクラク請求書受取・マネーフォワードクラウド請求書といったおすすめの請求書管理システムを比較形式で紹介します。
それぞれ機能性や料金プランに違いがあるので、自社に合った請求書管理システムを選ぶ参考にしてください。
| 機能 | 特長 | 電子帳簿保存法・インボイス対応 | おすすめの人・企業 | 費用目安 | アプリ対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| invox受取請求書 | ・請求書の取り込み ・請求書スキャンサービス ・会計システムやオンラインバンクとの連携機能 ・申請 ・承認フロー設定 | ・あらゆる形式の請求書受取に対応 ・請求書はAI OCRとオペレータが99.9%正確に自動でデータ化 ・会計システム、ERP、オンラインバンクとの連携性が高い・自社に合わせたカスタマイズが可能 ・シンプルで使いやすいUI設計 | 対応 | ・中小企業 ・大企業 | ・初期費用:0円~ ・ミニマムプラン:1,078円(月額) ・ベーシック:10,780円(月額) ・プロフェッショナル:32,780円(月額) ※プランによって機能制限有り | 非対応 |
| BillOne | ・請求書受け取り代行 ・請求書のスキャン代行 ・請求書の自動データ化 ・ステータス管理 ・ワークフロー設定 ・仕訳入力 | ・99.9%の精度で請求書をデータ化 ・請求書の受取から申請、承認、保管、経理対応まで完結 ・代理受領した紙の請求書を素早くデータ化保存 ・複数の拠点で受領した請求書も一元管理可能 | 対応 | ・中小企業 ・大企業 | 初期費用・年額費用無料(スモールビジネスプラン) ※スモールビジネスプランの請求書受け取り件数は100件/月まで無料 ※従業員数101名以上の場合は要問い合わせ | 非対応 |
| バクラク請求書受取 | ・請求書自動読み取り ・支払情報自動入力 ・支払金額レポート ・振込データ出力 ・会計システム連携 | ・過去の仕訳データを学習して自動入力 ・振込データを自動作成 ・レポート機能で受取状況や支払い状況を可視化 ・お問い合わせやウェビナーなどサポート体制が充実 | 対応 | ・中小企業 ・小規模事業者 | ・月額料金:44,000円~ ※契約は年間契約、12ヶ月分を一括払い ※ | 非対応 |
| マネーフォワード クラウド請求書 | ・帳票作成(適格請求書含む) ・請求書の定期発行 ・取引先や品目の自動入力機能 ・カード決済機能 ・売上レポート機能 | ・請求書の発行から保管まで一元管理できる ・初期費用0円ですぐに利用できる ・請求書の郵送やメール送付がワンクリックで完了する ・クラウド会計 ・確定申告との連携がスムーズ | 対応 | ・フリーランス ・自営業者 ・中小企業 ・大企業(上場企業) | <個人向け> ・年間プラン:月額990円〜、年額11,880円〜 ・月額プラン:1,408円〜 ※請求書郵送は1通あたり200円 <法人向け> ・年額プラン:月額3,278円〜、年額39,336円〜 ・月額プラン:月額4,378円〜 ※1ヶ月無料トライアル有り | 非対応 |
※:要問合せ
請求書の受領メールに関してよくある質問

最後に、請求書の受領メールについてよくある質問を紹介します。
- 請求書の受領メールに対して返信は必要?
- メールで受領した請求書をそのまま保存しても良い?
- 電子帳簿保存法に準拠して請求書を保存する方法は?
それぞれの質問にお答えするので、疑問点や不明点がある企業はここで解消しておきましょう。
請求書の受領メールに対して返信は必要?
請求書の受領メールに対する返信は、必ずしも必要ではありません。受領メールに対してお礼メールを送る企業も多いですが、取引先との関係性によって返信するか検討すると良いでしょう。
ただし、送信者が受領内容の確認を求めている場合や特定の対応を促している場合には返信が必要です。
メールで受領した請求書をそのまま保存しても良い?
メールで受領した請求書をそのままメールとして放置している状況は、電子データとして保存しているとはいえません。法令遵守の観点はもちろん、管理の効率化の観点から見ても適切な方法による保管が推奨されます。
メールで請求書が送られてきた場合は、受け取り方法に応じて適切に保管しましょう。
| メールによる請求書の受け取り方 | 請求書の保管方法 |
|---|---|
| PDFやExcelなどの形式で請求書がメールに添付されている場合 | ・添付されたファイルにタイムスタンプを付与しハードディスクやクラウドサービスなど別の媒体に保存する ・自社独自のメールシステムでメールごと保存する(メールの訂正や削除を確認できる、または訂正や削除ができない機能が備わっている場合) ・作成した事務処理規程に基づいて保存する |
| メール本文中に取引情報が直接記載されている場合 | ・メール自体にタイムスタンプを付与しハードディスクやクラウドサービスなど別の媒体に保存する ・自社独自のメールシステムでメール自体を保存する ・メールに記載された取引内容をPDFやスクリーンショットで保存する |
電子メール内に請求書をそのまま放置していると、ファイルが散逸するリスクが高まり、必要な情報を迅速に見つけられない可能性もあります。基本的にはメールから請求書をダウンロードし、専用のフォルダやサービスに保存し直すことが大切です。
電子帳簿保存法に準拠して請求書を保存する方法は?
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存要件を定めた法律です。電子帳簿保存法では「電子取引した文書は電子データで保存すること」が義務付けられており、電子データで受領した請求書は電子のまま保存する必要があります。
また、保存期間も定められており、請求書をはじめとする帳簿書類は確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。法律に準拠して請求書を保存するためにも、電子帳簿保存法の要件を満たしたクラウドシステムを導入しましょう。
参考:国税庁 | 電子帳簿等保存制度特設サイト、国税庁 | No.5930 帳簿書類等の保存期間
請求書の受領メールはマナーを守って素早く送ろう
本記事では、請求書の受領メールを送る目的や記載すべき内容のほか、ビジネスマナーや注意点などを解説しました。請求書の受領メールには、取引先に安心感を与え、請求処理をスムーズに進める役割があります。可能な限り素早く受領メールを送ることで、より丁寧で誠実な印象を与えられるでしょう。
なお、受領した請求書は電子帳簿保存法にしたがって保存する必要があります。監査で求められた場合に正しく提示できるよう、請求書管理システムを導入して適切に保管しましょう。
| 以下の問題でお悩みの方は、こちらのボタンからぜひお気軽にお問い合わせください。 ・自社に合った請求書管理システムを知りたい ・請求書の受領から処理を効率化できるシステムを選びたい ・導入や運用にかかる費用を知りたい |