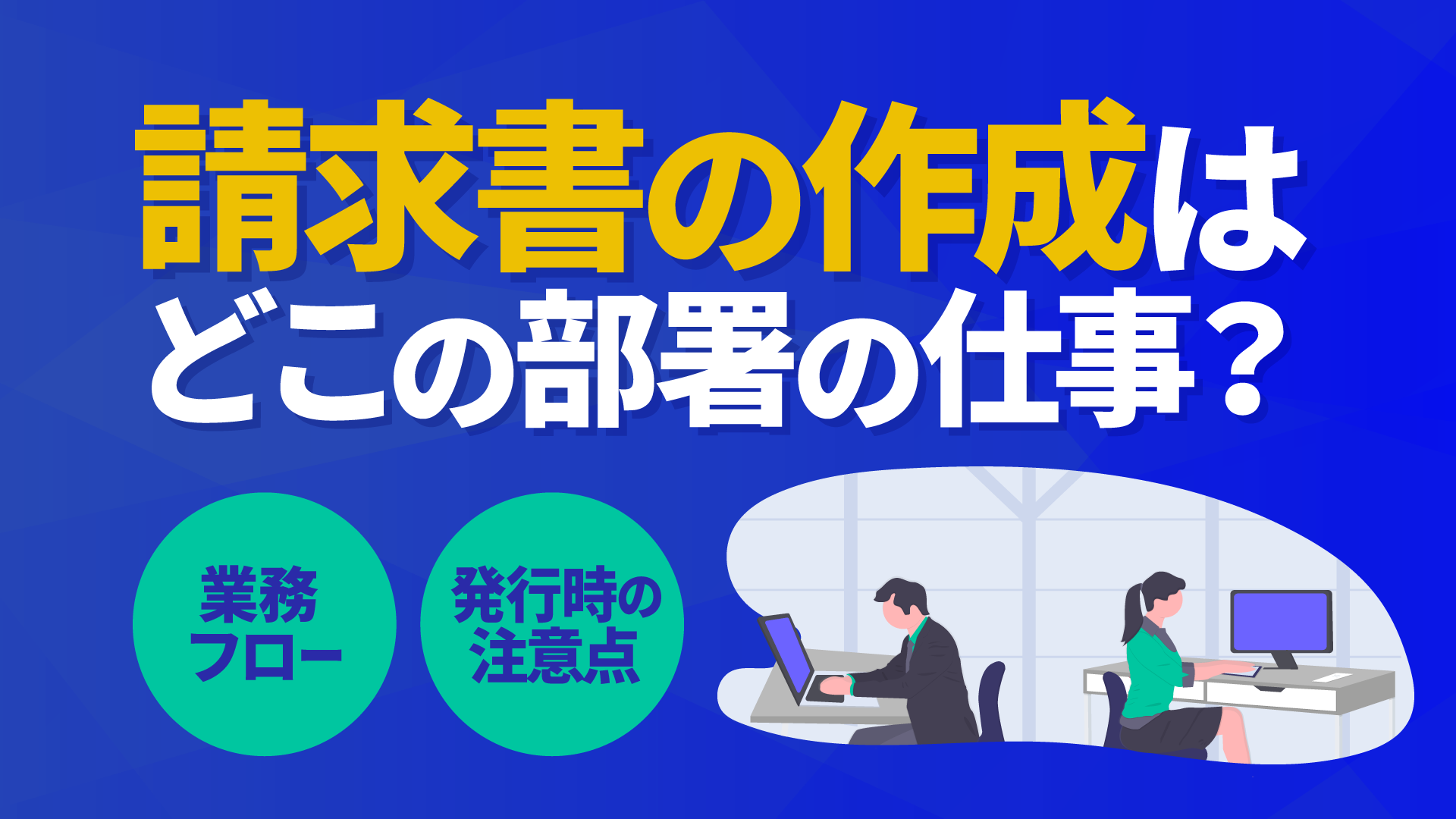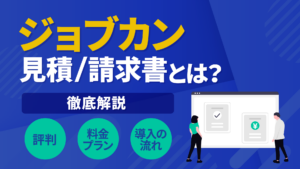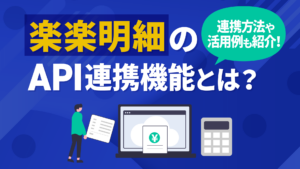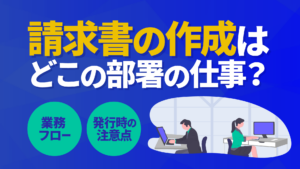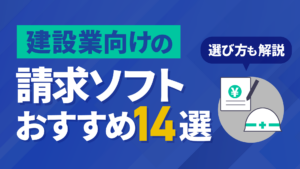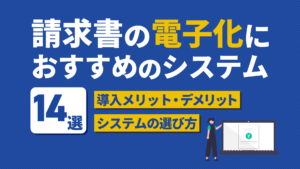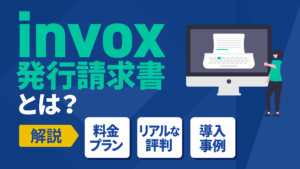企業経営に欠かせない請求業務は、請求書の発行から代金の回収まで多岐にわたります。正確性が求められる仕事ですが、どこの部署が担当すべきなのか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
請求書を作成するのは基本的に経理部門または営業部門となり、どちらが担当する場合にもメリット・デメリットがあります。複数の部署をまたいで請求書を発行すると情報が散逸する恐れがあるので、特定の部門で一括処理するのがおすすめです。
本記事では、請求業務の仕事内容や請求書作成を担当する部署について詳しく紹介します。請求書の発行処理における業務フローや注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
| ・効率的かつ正確に請求書を発行したい ・請求業務を効率化したい ・請求書システムの導入を検討している 上記のお悩みがある方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。 |
難しい?請求書業務の仕事内容とは

請求書業務とは、取引先に支払いを求めるための書類を作成し、管理する業務のことです。業種や業界を問わず必要な定型業務で、請求書の発行はもちろん、金額を計算したり支払い処理をしたりと業務内容は多岐にわたります。
特に多くの取引を抱える企業では、高額な金額計算や多量のデータ管理が必要となり、時間と労力がかかることも少なくありません。請求業務のミスは企業の信頼性にも関わるため、集中力と正確性を持って仕事にあたることが大切です。
なお請求書の発行は、法律で義務付けられているわけではありません。しかし「取引があったという事実の証明」や「取引金額や期日の明確化」のためには、請求書を発行して客観的な証拠を残しておくことが重要です。
取引先が消費税の仕入税額控除をする際にも請求書が必要なので、請求書の発行はあらゆる企業にとって必須といえる業務でしょう。
請求書を作成するのはどこの部署・職種?

請求書作成を担う部署や職種は組織体制によって異なりますが、経理部門や営業部門が担当する企業が多い傾向にあります。ここでは、請求書を担当する職種や部署について詳しく見ていきましょう。
経理部門
経理部門は、企業活動における財務管理を担う部署です。企業の資金の流れを適切に管理し、会計業務を通じて経営に必要な財務情報を提供します。日々の取引の記録から決算、税務処理まで幅広い業務を行っており、請求書の発行も経理部門が担当するのが一般的です。
売上データや顧客情報を基に請求書を作成し、発行後の入金管理や債権管理もまとめて経理部門で一括処理すれば請求業務全体を管理しやすくなります。
営業部門
企業によっては、営業部門が請求書の発行を担当するケースもあります。取引の最前線に立つ営業部門は顧客との取引条件に精通しているため、スピーディーに請求書を発行できるのが特徴です。
特別な支払い条件や記載内容を求められた場合も、顧客の意図を正確に反映した請求書を作成しやすいでしょう。
ただし営業部門の本来の仕事は、請求業務でなく顧客との商談や契約交渉です。経理部門に比べると専門知識に乏しく、数字の処理や帳簿への記載でミスが発生するリスクもともないます。
経理担当者が請求書を作成するメリット・デメリット
| 経理担当者が請求書を作成するメリット | 経理担当者が請求書を作成するデメリット |
|---|---|
| ・消費税や法的要件を正しく反映できる ・請求書のフォーマットや管理方法を統一できる ・営業部門による不正を防止できる・業務の属人化を防止できる | ・経理担当者の業務負荷が増大する可能性がある ・取引内容を詳細に把握できないため、営業部門と連携する必要がある |
経理部門は会計や税務といった専門知識を有しているため、信頼性の高い請求書を作成できるのがポイントです。入金予定日や取引金額などもすでに把握しているため、入金消込や入金後の領収書発行などもスムーズに行えます。
また取引から請求までの業務に経理担当者が介入することで、業務の属人化や営業部門による不正を防止できるのもメリットです。
しかし経理部門は決算や資金管理など普段から多くの業務を抱えているので、請求業務が大きな負担となる場合もあります。特に月末や期末などの繁忙期には業務が集中し、作業効率が低下するリスクも考えられるでしょう。
業務負荷が増大するだけでなく、タイムリーな請求書発行が難しいのもデメリットのひとつです。経理部門は顧客との直接的な接点が少ないため、取引内容の詳細を把握するには営業部門との密な連携が必要になります。
営業担当者が請求書を作成するメリット・デメリット
| 営業担当者が請求書を作成するメリット | 営業担当者が請求書を作成するデメリット |
|---|---|
| ・顧客のニーズに合った請求書を迅速に作成できる ・顧客からの問い合わせにもスムーズに対応できる | ・営業活動に割く時間が減少する ・個々の営業担当者に一任されると業務の属人化が進む ・専門知識の不足により、請求内容にミスが生じるリスクがある |
営業担当者が請求書を作成すれば、顧客のニーズに合った請求書を迅速に作成できるのがメリットです。顧客との取引条件や契約内容を詳細に理解しているので、請求後に問い合わせがあったときにも柔軟に対応できます。特に取引先によって特別な条件が設定されている場合は、営業担当者が作成することでミスを未然に防げるでしょう。
しかし営業担当者は、新規顧客の開拓や商談に多くの時間を割いているため、請求書作成が追加されると業務負担が増加する可能性があります。税務や法的要件に対する知識が不足している場合も多く、内容に誤りが生じるリスクがあるのはデメリットです。
営業担当が請求書を作成する場合は、経理部門が最終チェックを行ったり請求書発行システムを導入したりと、効率的に業務を進められる仕組みを整えることが大切です。
請求書は経理部門で一括処理するのがおすすめ

請求書に関する業務は、基本的に経理部門で一括処理するのがおすすめです。経理担当者は売上情報や取引先データを把握しているため、請求書作成に必要な情報をスムーズに収集できます。
発行後の入金確認や債権管理も一貫して行えるので、キャッシュフロー管理が容易になるでしょう。また、経理部門で一括処理することで営業部門が本来の業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上する利点もあります。
ただし経理部門に業務が集中してしまうので、負担軽減や作業の効率化を目指すなら請求書発行システムの導入が有効です。
請求書を発行するタイミング

請求書の発行タイミングは大きく締め請求と都度請求に分けられ、取引条件や契約内容に応じて適切なタイミングが異なります。
発行のタイミングを誤ると、取引先からの信頼を損ねたり支払い遅延が発生したりするリスクがあるため、契約時には発行スケジュールを明確に設定しておきましょう。
締め請求
締め請求は、一定の期間内に行われた取引を集計し、まとめて請求する方法です。月末や月中など決められた締め日を設け、その期間内の取引を一括して請求します。
締め請求は請求書の発行頻度を減らせるため、複数の取引が発生する顧客への請求に適しています。顧客側にも支払いをまとめて行えるメリットがあるため、双方ともに請求管理をしやすくなるでしょう。
しかし取引内容や金額が多い場合は、締め日に向けて請求書作成業務が集中するため、繁忙期の負担が増加する可能性があります。遅れが生じると発行タイミングがズレるリスクもあるので、余裕を持って取引データの集計を進めることが大切です。
都度請求
都度請求は、取引が発生するたびに請求書を発行する方法です。取引内容を逐一確認できるため、顧客との間で誤解が生じにくい利点があります。単発の取引や少額の取引が多い場合に適しており、顧客が即時に支払いを行う必要がある取引にも有効です。
しかし頻繁に請求書を作成しなければならないため、手作業では業務負荷が増大する可能性があります。支払い日も分散するので、企業のキャッシュフロー管理が複雑になることも考えられるでしょう。
【図解】請求書の発行処理の業務フロー

請求書発行処理は、主に以下4つの流れで実施します。
- 請求内容を確定する
- 請求書を作成する
- 請求書を送付する
- 入金消込を行う
ここでは、請求書の発行から処理における業務フローを詳しく見ていきましょう。
1. 請求内容を確定する
請求書を発行する前に、まずは請求内容を正確に確定する必要があります。取引先との契約内容や納品状況、提供した商品やサービスの明細を確認し、請求金額を計算しましょう。
特別な割引や条件が適用されている場合は、内容を請求書に正しく反映させることが重要です。税率や消費税の計算にも間違いがないよう、細心の注意を払ってください。不正確な情報が請求書に記載されると、クレームや支払い遅延の原因となるため注意が必要です。
2. 請求書を作成する
請求内容が確定したら、専用のシステムやテンプレートを使用して請求書を作成します。請求書には、請求日や支払い期日など以下のような法定記載事項を記載しましょう。
| 請求書への記載項目 | 注意すべきポイント |
|---|---|
| 発行日 | 支払い期日や遅延の有無を確認する基準となるため、空欄にせず必ず記載する |
| 請求先の会社名や担当者名 | 取引先の会社名(担当者名)や住所を記載。敬称の使い分けに注意する |
| 発行側の会社名や担当者名 | 自社の社名や担当者名のほか、住所や電話番号を記載する |
| 取引の詳細(取引金額) | 製品・サービス名や品番・個数・単価などを記載。請求金額の仮合計は、小計として記載する |
| 支払い期日 | 契約内容に基づく支払い期日を記載。支払い期日を誤記すると、支払遅延や未払いが発生する可能性があるので注意する |
| 支払い先 | 銀行名、支店名、口座番号、口座名義などを間違えずに記載する |
支払いに必要な情報が抜けていると、取引先もスムーズに処理を進められません。適格請求書(インボイス)を発行する場合は、登録番号や税率ごとに区分した消費税額などの記載も必要になるので事前に確認しておきましょう。
3. 請求書を送付する
請求書の作成後は、社内での承認フローを経て取引先に送付します。送付方法は郵送やメールが一般的ですが、最近では請求書システムを通じて送る企業も増えています。
郵送には印刷や封入の手間がかかるので、請求書の発行が多い場合は電子システムを活用することでコスト削減と送付の迅速化が図れるでしょう。
なお請求書の送付後は、顧客が確実に受け取ったことを確認することが重要です。取引先から受領メールが送られてこない場合は、一度確認の連絡を入れてみてください。
4. 入金消込を行う
最後に、顧客からの入金を確認し、消込処理を行います。消込処理とは、入金金額と請求金額を照らし合わせ、正しく支払われているかを確認する作業です。
未収金や過剰入金が発生していないかチェックし、不一致がある場合は速やかに取引先に問い合わせましょう。入金消込が適切に行われなければ帳簿のズレが生じ、後々の会計監査やキャッシュフロー管理に悪影響を与える恐れがあります。
入金消込機能が搭載された請求書管理システムなら、銀行口座と連携して自動的に入金情報を取得・処理できるのが魅力です。
請求書を作成する際の注意点

請求書の作成は一見単純に思える作業ですが、いくつか注意したいポイントがあります。
- 請求日や支払い期日を確認しておく
- 宛名が会社か個人かによって敬称を使い分ける
請求書に記載する内容は取引先と決める必要があるので、事前に情報をすり合わせておくことが大切です。認識に相違があると後々のトラブルに発展するため注意しましょう。
請求日や支払い期日を確認しておく
請求書を作成する際は、請求日や支払い期日といった記載内容を取引先とすり合わせておくことが大切です。基本的に請求日は、請求書を作成した日ではなく請求先の締め日に応じて記入します。企業によっては納品日に合わせる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
請求日を決めたら、支払い期日を設定します。取引先との合意があれば自由に設定できますが、月末締め・翌月末支払いまたは翌々月末支払いが一般的です。
なお下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、下請事業者との取引における支払い期日が定められています。下請法の適用業者と取引する場合は、下請事業者からの給付を受領後60日以内かつ可能な限り短い期間で支払い期日を定めなければいけません。
ほかにも、振込手数料の負担者や消費税の扱いについては事前に取引先と確認し、契約書に記載しておくと良いでしょう。
宛名が会社か個人かによって敬称を使い分ける
請求書の宛名は、会社か個人かによって敬称を使い分ける必要があります。会社の場合は「御中」、個人名の場合は「様」を敬称として記載します。請求先の担当者が不明なときは、会社名だけでも問題ありません。
また、会社宛であっても担当者名を明記する際は「株式会社〇〇 △△様」と記載します。個人名の後に役職名が記載されている場合も、敬称を省略せず「株式会社〇〇 △△部長 ◇◇様」と明記してください。
宛名の敬称を誤ると失礼にあたるため、正しいマナーを確認しておきましょう。
請求書発行業務における課題

請求書の発行業務には多くの課題があり、効率化を図らなければ業務負担が増加する可能性があります。
- 手作業によるミスが生じる恐れがある
- 属人化のリスクがある
- 請求書の保管期限を守る必要がある
ここでは請求書の発行業務で直面しやすい課題を解説するので、事前に解決策を考えておきましょう。
手作業によるミスが生じる恐れがある
請求書の発行を手作業で行っている場合、記載ミスや金額の誤りが発生するリスクがあります。顧客情報や請求金額のミスは、取引先との信頼関係を損なう原因となるため注意が必要です。
特に大量の請求書を処理する場合は、手作業によるミスが生じやすくなります。請求書の発行業務を正確に進めるためにも、クラウド型の請求書作成ツールや会計システムを導入するのがおすすめです。
事前に登録した顧客情報やテンプレートを利用して自動化できるため、ミスを防止できるだけでなく担当者の負荷軽減にもつながります。
属人化のリスクがある
請求書発行業務が特定の担当者に依存している場合、属人化のリスクが発生します。属人化が進んでいると、担当者が休暇を取ったり退職したりする際に業務の引き継ぎが難しくなります。
特に担当者固有のフォーマットや手順が用いられている場合は、新しい担当者への引き継ぎで業務が滞る可能性もあるでしょう。
属人化のリスクを軽減するには、業務プロセスを標準化することが大切です。クラウドベースのシステムを利用すれば、請求データを複数の担当者で共有できるので、特定の担当者が不在でもスムーズに作業を進められます。
請求書の保管期限を守る必要がある
発行した請求書は、法的な要件に基づいて一定期間保管しなければいけません。電子帳簿保存法に則って確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保管が必要となり、適切に保管されていない場合は税務調査で問題が生じる恐れがあります。
特に紙媒体で請求書を発行・管理している企業は、保管スペースの確保や紛失のリスクが大きな課題になります。請求書の検索性や管理効率を向上させるためにも、請求書発行システムを導入するのがおすすめです。
請求書の発行業務にシステムを導入するべき理由
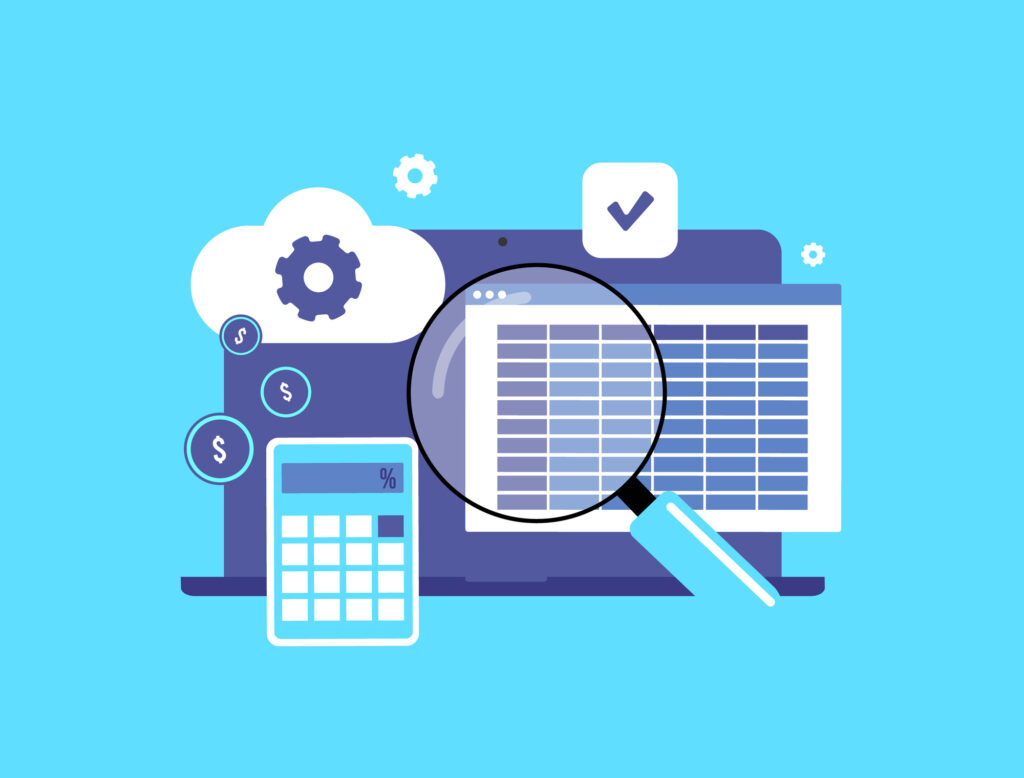
請求書の発行業務を効率化したいなら、専用のシステムを導入してみてはいかがでしょうか。請求書発行システムを導入すれば、請求書作成・送付・管理といったプロセスを自動化でき、作業時間を大幅に削減できます。
- 請求書のフォーマットを統一できる
- 請求書を複数名で共有できる
- 請求業務が効率化する
- コストの削減につながる
本章では、請求書の発行業務にシステムを導入するメリットを詳しく解説します。
請求書のフォーマットを統一できる
請求書発行システムを導入すれば、請求書のフォーマットを自動的に統一できます。社名や住所といった記載内容を毎回入力する手間が省けるほか、抜け漏れがなくなるのもメリットです。
また取引先によって異なる内容を記載する場合も、システム内で複数のテンプレートを登録しておけば、簡単に切り替えられます。請求書発行システムのなかには現行の請求書デザインを再現できるものもあるので、導入後もスムーズに運用できるでしょう。
請求書を複数名で共有できる
請求書発行システムは、請求データを複数名でリアルタイムに共有できるのが特徴です。特定の担当者以外もデータにアクセスできるため、業務の属人化防止につながります。
またクラウド型のシステムであれば、営業と経理のように拠点が離れていてもスムーズに情報を共有でき、部門間の連携を強化できます。テレワークが普及している企業なら、場所を問わず請求業務を進められるのもメリットです。
請求業務が効率化する
請求書発行システムによって電子化を進めれば、請求書の作成や送付にかかる作業時間を大幅に短縮できます。顧客情報や取引内容といった請求書作成に必要なデータもシステムが自動で取り込むので、手作業での入力が必要ありません。
担当者の負担軽減やヒューマンエラーの防止はもちろん、未送信の請求書や未入金の状況も一目で把握できるため業務の透明性が向上するでしょう。会計システムと連携可能なシステムなら、入金消込作業もより効率的に行えます。
コストの削減につながる
請求書を紙媒体で発行していると用紙代・印刷費・郵送費などがかかりますが、電子の請求書発行システムではこれらのコストを削減できます。また人の手による作業が少なくなるため、人件費を削減できるのも魅力です。
請求書発行システムの利用には初期費用や月額費用が発生しますが、長期的な目線で見ると経済的なメリットが大きいといえるでしょう。料金プランはシステムによって異なるため、機能性やサポート体制なども加味したうえで、費用対効果の高いシステムを導入するのがおすすめです。
部署連携を通じて効率的な請求書作成を
請求書の作成は、経理部門または営業部門が担当するのが一般的です。複数の部署をまたいで請求書を作成すると誤りや業務の重複が発生しやすくなるので、可能な限り企業の金銭管理を行う経理部門で一括処理すると良いでしょう。
営業部門と連携できる環境を整備しておけば、詳細な取引内容に基づいて迅速に請求書を作成できます。また請求書の発行から管理までの業務を効率化したいなら、請求書発行システムを導入するのもひとつの方法です。
郵送費や印刷代などのコストを削減できるだけでなく、請求書を複数名で共有できるため請求業務の属人化を防止できます。部門連携の強化にも役立つため、正確な請求書作成を叶えたいという企業はぜひ導入を検討してみましょう。
| 以下の問題でお悩みの方は、こちらのボタンからぜひお気軽にお問い合わせください。 ・自社に合った請求書管理システムを知りたい ・請求書の発行から管理までを効率化できるシステムを選びたい ・導入や運用にかかる費用を知りたい |