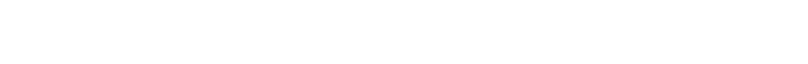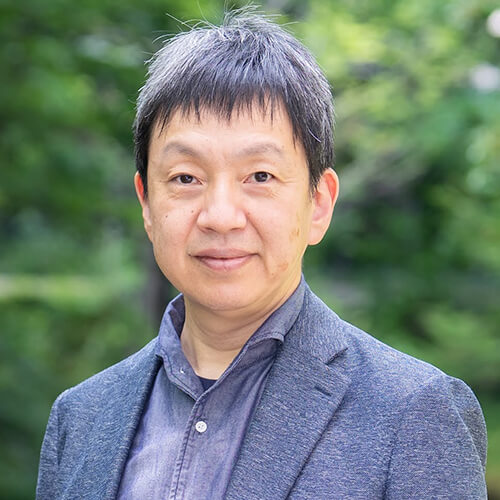生成AIの登場により、情報収集やコンテンツ制作のあり方は劇的に変化しています。誰もが簡単に「正解らしい」答えにたどり着ける時代、マーケターは自らの専門性をどう発揮し、顧客や社会に価値を提供していくべきなのでしょうか。
今回、その問いに答えてもらうのは麗澤大学工学部の清田陽司教授です。清田教授は京都大学で自然言語処理を専攻して以来、AI研究の道を歩み、東京大学助教在籍中には大学発スタートアップを共同創業しました。現在は、株式会社FiveVai 取締役、株式会社LIFULL 主席研究員、情報科学技術協会(INFOSTA)会長など、学問・産業の両分野で活躍しています。
長年にかけてアカデミックとビジネスの両面からAIの進化を見つめてきた清田教授に、当社執行役員の月岡克博が今後のマーケター、企業の生存戦略を伺いました。
AI時代に求められる「問いを立てる力」と「哲学」
月岡:
まずは清田先生の、これまでの経歴について教えてください。どのような経緯を経て、アカデミアとビジネス両方のキャリアを積むに至ったのでしょうか?
清田:
私のキャリアの原点は、1997年に京都大学で自然言語処理の研究室を選んだことから始まりました。
修士課程では自動要約、博士課程ではマイクロソフトとの共同研究で対話システムの研究などに携わりました。今でこそ、ChatGPTへの指示ひとつで優れた結果が出力されますが、当時は賢い対話をどう実現するかという試行錯誤の連続でした。
その後、東京大学の教員になり、図書館のサービスを自然言語処理でどう良くできるかという研究に携わりました。その技術を元に2007年に大学発スタートアップを共同創業し、図書館向け以外にもビッグデータ解析の事業などを展開しました。
2011年にLIFULL社の傘下に加わり、同社の強力なサポートのもと、不動産テック分野の研究開発に取り組むようになります。そして現在は大学に戻り、学生たちにAIやソフトウェア工学を教えています。

月岡:
まさに研究とビジネスの最前線を行き来してきたのですね。今やAIは、世界の人々が当たり前に活用する時代になりました。清田教授から見て、今後私たちの「情報の探し方」はどう変わっていくと思いますか?
清田:
ある意味で「二極化」していくと考えています。一つは、多くの人が便利なツールとしてAIに依存していく流れ。これはスマホが生活に不可欠になったのと同じで、不可逆の流れといえるでしょう。
一方で、プロとして仕事をする人々には別の道が求められます。私も大学教員という仕事をして対価としての報酬をいただいていますが、プロフェッショナルとしてお客様や社会に価値を提供するためには、多くの人と同じようにAIに依存しているだけでは存在意義がなくなってしまう。
プロとして生き残るためには、その領域における専門性を確立し、AIという道具をどう使いこなして独自の価値を提供できるかが重要になると思います。その専門性や独自価値の確立のために、業界内のポジショニングや顧客ニーズをさらに追求していくことになるでしょう。
月岡:
どんなに高性能なパソコンを渡されても、使う人が「1 + 1」の計算しかしないのか、それとも複雑なシミュレーションに活用するのかで、生まれる価値が全く違ってくると思います。AIによって生産性や効率性が向上できるようになったとしても、その価値を享受できるかはプレイヤーのプロフェッショナルにかかっているのかな、と。
AI時代において、清田教授はForbesへの寄稿記事(※)で「問いを立てる力」の重要性を説いていますよね。「問いを立てる力」とは、どうすれば磨けるのでしょうか。
※参考:Forbes 清田教授 著「ググる」は本当に死ぬのか? 生成AI時代、AI科学者はこう検索する
清田:
問いを立てる力の根幹は、その人の中にある「哲学」なのだと思います。
月岡:
哲学ですか?
清田:
哲学と聞くと、カントやヘーゲルなど先人の考えを探求するといった、難解なイメージがあるかもしれません。しかし、本来の哲学は私たちの非常に身近な問題を扱う学問です。「人はなぜ生きるのか」「愛するとは何か」。こうした根源的な問いに向き合うのが哲学です。
あらゆる学問の親は哲学なのです。物理学も工学も、元をたどれば哲学に行き着く。同じ工学でも、機械工学や電気工学、情報工学など学問が細分化された現代において、異なる分野の専門家が唯一共通言語で対話できるのが、哲学の言葉です。
取材進行スタッフ:
言葉を濁さず言えば、哲学と聞くと「偏屈な人がやるもの」といったイメージがあったので、清田教授の回答は少し意外でした。
清田:
そう思われてしまうのは仕方ないかもしれません(笑)。私の師匠は、「日本の哲学者で、本当の意味で哲学をやっているのは1割くらいだ」とおっしゃっていました。残りの9割は、カントがなぜそう考えたかを解き明かすような「哲学学」をしていると。
哲学学も大切な研究です。しかし本来の哲学の面白さは、現代社会の身近な問題を扱い、考えることにあります。
月岡:
なるほど。身近な問題に対して「なぜそうなのか?」と問い続けること。そうした哲学的な思考を深めることが、AI時代に価値を生む「良い問い」につながっていくということですね。

学問、フィールドワーク、遊び。あらゆる土壌から学ぶ
月岡:
マーケターにとって、清田教授の言う「哲学する力」は今後非常に重要な能力だと思います。この力を鍛えるには、どうすればいいのでしょうか?
清田:
一つは、「なぜそうなのか」と問い続ける思考訓練をすることです。そしてもう一つ、そのためにはある程度、幅広い学問の土壌を持っておくことが必要です。数学、国語、歴史、古典といった教養が、一見すると無意味に思えても、そうした土台がないと、そもそも哲学の重要性が体感的にわからないのです。
月岡:
学び続けることが大事ですね。ただ、社会人になると学ぶ機会を作るのが難しいというのも現状あると思います。
清田:
「学ぶ」というと、多くの日本人が学校の教室で先生の話を聞き、ペーパーテストをクリアすることだと考えがちです。しかし、学びのスタイルはそれだけではありません。
セミナーに参加するのも学びですし、フィールドワークも非常に重要です。私もLIFULLでは、空き家問題の解決策を探るために空き家を活用している人のもとへ足を運んで話を聞き、夜は一緒にお酒を飲みながら語り合いました。
そうした現場での対話から得られる学びは非常に大きい。極端に言えば、「遊び」も学びのうちなんです。現代人は、学び方を不器用に捉えすぎているのかもしれません。
月岡:
たしかにそうですね。私はマーケティングを学ぶ私塾に参加しているのですが、そこでは普段会えない人と会うことができ、大きな学びとなっています。現地調査などはAIにはできませんし、まさに人間ならではの価値につながる行動ですね。
一方で、先生のようなアカデミックなアプローチ、つまり体系的に学問を学ぶことも重要ではないでしょうか。特にマーケティング界隈では、根拠の曖昧な「自分勝手理論」が語られることも少なくありません。

清田:
おっしゃる通りです。学問とは、先人たちが何を積み重ねてきたかを踏まえた上で、自分は何を拡張するのかを問う世界です。先人へのリスペクトの上に自らのオリジナリティを明らかにする。このアカデミアの作法は、マーケティングの知識を深めるうえでも非常に重要です。
ただ、日本のアカデミアには課題があります。研究には、誰も見つけていない新たな知見を探求する「シーズ志向」のアプローチと、特定の課題を解決するためにさまざまな分野の知見を結集する「ニーズ志向」のアプローチがあります。理想はこの両輪がバランスよく回っていることですが、日本のアカデミアではどうしてもシーズ志向に偏りがちです。
新しい理論や技術の新規性ばかりが問われ、それが「社会でどう役立つのか」という視点が軽視されることがある。産業界とアカデミアの間で、そうしたすれ違いが起きているのも事実です。このすれ違いが起きたまま学んだり議論すると、徒労に終わってしまうことがあるので注意が必要ですね。
「自分たちならではの物語」をどう作るか。AI時代の企業戦略
月岡:
AI時代を迎え、生活者と企業が発信する情報との関わり方は大きく変わると思います。最近では、生活者に届けられる情報のパーソナライズが過剰に進行し、かえって個々人の視野が狭くなる「フィルターバブル」の問題が指摘されています。清田教授はどう考えていますか?
清田:
モノからコトへと消費が移る中で、生活者は「自分なりの物語」を求めているように感じます。社会の中でどう貢献したいか、どんな存在価値を示したいか。そうした欲求に応える物語です。
一方で、多くの人と共有できる大きな物語への渇望も、心のどこかにあるはずです。昭和の時代、誰もがTV番組の『8時だョ!全員集合』を観て、週明けはその話題で盛り上がった。今はそうした共通体験が希薄になりましたが、だからこそ人々は、共に参加して共創できる物語を求めているのではないでしょうか。
月岡:
最近、企業がファンコミュニティを作り、消費者を巻き込んで製品開発を行う共創の動きが活発ですが、それも同じ文脈だと言えそうです。そうした変化に対して、企業やマーケターはどう向き合っていくべきでしょうか?
清田:
各プラットフォーム上で手に入る情報は、どんどんコモディティ化していきます。その中で企業が生き残るには、「自分たちならではの共有できる価値」を、顧客と共に作っていく。そうした活動にこそ、人々は意義を見出すのだと思います。
「私だけが知っている」「私が関わった」という体験が物語となり、ブランドへの強いロイヤリティにつながっていく。これからの企業戦略の鍵は、そこにあるのではないでしょうか。そして、その独自価値の源泉となるのが、「自分たちしか持っていないデータ資源」です。
すでにAIによる機械学習は、人間が制作した入手可能な文字情報をほぼすべて学習し終えたとさえ言われています。そうなると、今後AIは「AIが生成したテキスト」を学習することになる。その結果、AIが生成したテキストを学習し続けることで、出力の品質が劣化する『モデルコラプス(model collapse)』と呼ばれる現象も報告されています。
例えば最近、論文のなかに見慣れない単語や表現が散見されるようになりました。私はある英文誌の副編集長をしていますが、最近生成AIによって書かれたと思われる論文の投稿数が日に日に増えています。その内容を見ると、「なんじゃこりゃ」と思う論文も増えているのです。
さらに言えば、LLM(Large Language Model ※大規模言語モデル)のトレーニングデータはアフリカなどの英語話者が書いているという話があります。人件費の問題でそうせざるを得ないのですが、彼らの使う英語の方言などが学習データに盛り込まれることで、いち地方でしか使われない表現や単語が学習されるという現象も起きているのです。
こうなると、人間が生み出した一次情報、特に企業が独自に持つデータの価値が相対的に高まります。自社ならではのデータベースや、顧客との対話から得られたテキストをどれだけ持っているか。それが、AIを活用する企業にとっての生命線になるかもしれません。

月岡:
例えば、企業のチャットボットログは顧客のリアルな悩みが入力されるから、それは「自分たちしか持っていないデータ」になりますね。それを分析してコンテンツやサービスの開発に活かす。そうした独自データを多く持つ企業が強くなるということですね。
清田:
おっしゃる通りです。長年培われた情報という、自社ならではの資産をどう構築して活用するかが、企業には問われています。
マーケティングにおいて、GoogleやMetaといった巨大プラットフォーマーが作った土壌の上で経済が動いている現実は、受け入れざるを得ません。しかし、その流れにただ乗っているだけでは、いずれエコシステムに生かされるだけの存在になり、最後はアルゴリズムに置き換えられてしまいます。
それが本当に社会や生活者にとって幸せなことなのか。今一度、考え直す時期に来ています。
月岡:
プラットフォーマーの仕組みに乗るだけではない、独自の価値を作ることが必要だと。具体的に何をすればいいのでしょうか?
清田:
一つの鍵は、プロフェッショナルとしての「矜持(きょうじ)」を持つことです。例えば医療の世界は、経済の力学が働きつつも完全な経済至上主義にはなっていません。国家試験や専門医制度があり、学会が品質を担保する。いわばプロの「ギルド」を形成し、業界としての秩序と価値を守っているのです。
Webマーケティングの業界も、プレイヤーが自分たちの価値は何かを定義し、健全な秩序を保つための努力を重ねていくことが必要ではないでしょうか。自主規制をしなければ、いずれ外部からコントロールされることにもなりかねません。
月岡:
我々のようなBtoBのSEO支援領域では、市場規模に対してプレイヤーが多すぎると感じることがあります。力を合わせるべきところは連合軍を組むことで、ギルドを形成し業界秩序を作るといった発想も必要なのかもしれません。 とはいえ、GAFAM(※)のような巨人たち以外で、そうした経済圏を成立させられるのか疑問が残ります。
※GAFAM:Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoftの5社の頭文字を組み合わせた略称
清田:
Webの世界だけで完結させようとすると、プラットフォーマーの言いなりになるしかありません。だからこそ、リアルの世界での情報と組み合わせたり、他業種と連携したりする努力が不可欠になります。あらゆる業界がAIによって「中抜き」される流れの中にあるからこそ、その領域だけではない価値を作っていく。これはどの業界にも共通する課題だと思います。
価値ある情報には対価を払うという時代の再来?
月岡:
ここまでの話を聞いていて、今後「情報の価値」は今後大きく変わると思いました。これまでWebコンテンツは無料で利用できるのが当たり前でしたが、今後は独自の情報を持つ企業や団体に対価を支払い、学習する流れがくる気がします。
清田:
そうですね。例えばLLMによる学習について、日本の規制は現在世界一ゆるいとされています。著作権法の第30条4項において、情報解析を目的とした著作物の利用に対しては、自由に利用できると定められているからです。
一方で、LLMの学習において著作者にまったくリターンがないのは問題ではないかという意見もあります。先日、とある省庁にてオープンデータの提供に従事されている方から、こんな話を聞きました。その省庁では、オープンデータを自由にダウンロードできるWebサーバーを運用しているのですが、AIから膨大な情報が取得されており、サーバーの運用負荷が著しく上がっているそうです。
サーバー運用のコストは基本的に運用者側が負担し、利用者側は無料で情報を入手できます。コストの一部はWeb広告収入などで補われていますが、AIは広告を見ても商品を買ってくれませんし、トラフィックも生みません。この状況で、いつまで無料でサービスを継続できるのかという不安が、オープンデータに関わる方々にも募っているようです。
このままいけば、「価値のある情報には対価を払う」という、当たり前の時代に戻っていくでしょう。
月岡:
冊子や本を買っていた時代が再来するわけですか。
清田:
問題は、情報や学びに価値があるとわかっていても、個人や企業がそこにお金を払うことにためらいがちになっていることです。特に日本ではその傾向が強いと感じます。その参加費がたとえ数千円であったとしても、です。
月岡:
研修やセミナーに参加することの効果を短期的な費用対効果で問われると、説明が難しいという話ですね。
清田:
今のような状態になった背景には、目標管理制度の普及が関係していると考えています。
INFOSTAはかれこれ75年の歴史を持つ団体ですが、今も存続している背景には、コミュニティでお互いにリソースを出し合い相互研鑽を重ねられる枠組みがあるからです。当団体の維持会員には製造業の企業も多いのですが、こうした会員企業には、競合他社の知財や特許などを調べる「サーチャー」という情報の専門家がいます。
一社でそうした人々の研鑽を続けるのは難しいので、コミュニティ内で知見を共有して研修会を開いたり、検定試験を作ったりしてスキルを高め継承していきました。また、研修後には懇親会などがあり、多種多様な人々が交流して学びを深める機会も作ってきました。
目標管理制度の導入以前、上司の裁量で「これは必要だから参加してこい」と、勤務時間内に研修やその後の懇親会に参加させてもらえました。しかし1990年代後半に目標管理制度が普及して以降、定められた目標を達成するためにどのようなプロセスを経て、どのように時間を使うかをマネジメントする必要が生まれました。
すると、研修やセミナーなど目に見えにくい価値に投資する意義を説明するのが難しくなり、結果「やらない」という選択を取り始めたのです。
月岡:
プロフェッショナルの醸成にコミュニティがひと役買っていたのに、目標管理制度をきっかけにその恩恵が受けられなくなってしまったと。
プロフェッショナルは人の中で磨かれる
清田:
AI時代にはやり方、つまり「ハウツー」の情報は瞬時に手に入ります。しかし、「そもそもなぜそれをやるのか」という問いの答えは、誰も教えてくれません。プロフェッショナルとは、多様な人との関係性の中で、自分自身で見つけるしかないのです。
コミュニティの意義は、まさにそこにあります。自分が何のためにこの仕事をするのか、自分のミッションは何か。それを明らかにする場として、コミュニティは機能するのです。
月岡:
なぜやるのかという自分の意思が、より明確に求められる時代になるわけですね。
清田:
今後、自らの志を言葉にすることはますます重要になると思います。自分の考えを言葉にして、人に広くシェアする。その過程で、志を同じくする人とつながる機会が生まれ、「この人と会ってみるのはどうか」という関係性へと発展していく。
それを繰り返すことで、チームやプロジェクトを動かせるようになり、世の中の仕組みを変えるエネルギーを生み出せるのだと思います。
こうしたつながりの創出にこそ、コミュニティの意義があると思います。INFOSTAでも、さまざまな機会にミートアップや懇親会を開催しています。最近の若い世代の方々には、こうした集まりの意義をあまり伝えられていないかもしれません。しかし、コミュニティに入り人と交わる経験がないと、プロフェッショナルは磨かれません。
オンライン上で見聞きすることで手に入る知識は、所詮インスタントなものに過ぎません。そうした知識を押さえておくことは重要ですが、目の前の人を幸せにするアウトプットをするために、その技術をどこで磨きますか?この疑問と、コミュニティで自分のプロフェッショナルを磨く重要性を、これからも伝えていこうと思います。

(執筆・サトートモロー、撮影:中林 正二郎、 進行・編集:前田絵理)
※関連記事:
・AI検索対応を急ぐ必要がない4つの理由と、いま考えるべき2つのポイント(辻 正浩 著)
・LLMOとは? マーケに活かす5つの対策をわかりやすく解説(月岡克博 監修)
・GEOとは? AI検索時代のSEO戦略と実践4ステップ
※Faber CompanyのLLMO(通称AI検索・AIO・GEO)支援サービス
・まずは情報収集したい➡︎ LLMO(GEO) 情報セミナー
・自社LLMO診断したい ➡︎ LLMO (GEO)チェックリストを無料ダウンロード
・専門家に相談をしたい➡︎ LLMO(GEO) 対策コンサルティング (30分無料)
・ツールを試してみたい➡︎ LLMO(GEO) 支援ツール「ミエルカGEO」