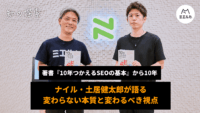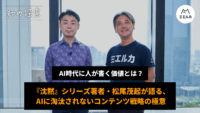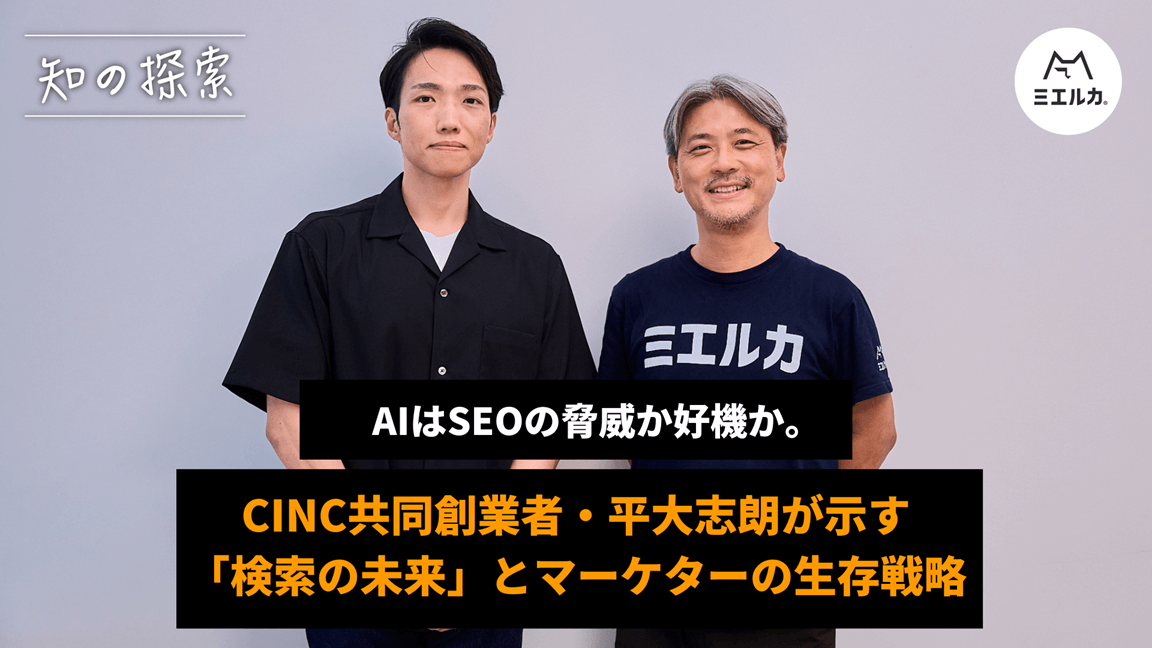 様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは、当社の本田卓也が務めます。
様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは、当社の本田卓也が務めます。
今回のゲストは、株式会社TechFabricの代表取締役社長であり、YouTubeチャンネル「SEO研究チャンネル」でも知られる平大志朗さんです。
東証グロース上場企業・株式会社CINC(シンク)の共同創業者として、そして「SEO研究チャンネル」の運営者として。平さんの足跡は、多くのSEOマーケターに影響を与えています。
幼少期に抱いていたものづくりへの情熱、海外での生活とSEOとの出会い、就職、データソリューションカンパニー・株式会社CINCの創業と上場、そして退任。さまざまなキャリアを重ねた平さんが、AIで根本的に変わろうとする検索体験に何を思うのでしょうか?
(執筆・撮影:サトートモロー 進行・編集:本田卓也)
プログラミングに没頭した海外でのSEO原体験
本田:
平さんとは最近、よくご飯などご一緒していますが、実はまだ知らないことがたくさんあるので、今日は興味のおもむくままにいろいろお聞きしたいと思います。まずは平さんの原体験を探りたいのですが、幼少期はどんな子どもだったのですか?
平:
昔からとにかく「ものづくり」が好きでした。小さい頃は木工に夢中で、岐阜県の県知事賞をいただいたこともあります。小学校のときは、夏休みの自由研究などでずっと木で何かを作っていました。
本田:
図工が得意だったのですね。それと岐阜のご出身とは知りませんでした。
平:
そうなんです。岐阜の南に位置する美濃地方で、小中学校を過ごしました。
本田:
スポーツはしていたのですか?
平:
中学まではそれほどやっておらず、高校や大学から水泳やランニングを始めた程度です。
本田:
これまでに取材したSEO業界で活躍する人たちは、ゲームや音楽など何かにハマったオタク気質の人が多い印象があります。平さんの場合はそれが「ものづくり」だったのですね。
平:
そうですね。私も例にもれず、生粋のオタクだったと思います(笑)。
本田:
先ほど「小中学校まで美濃で育った」ということですが、それ以降はどこで暮らしたのですか?
平:
高校3年間はニュージーランドに留学しました。当時、父が新聞でGoogleの成長に関する記事を読み、「これからは欧米圏だ。まず英語を学べ」と勧めてくれたのがきっかけでした。いきなりアメリカは危険だろうということで、安全なニュージーランドになったんです。
本田:
高校生から一人で海外に行くとは、思い切った決断ですよね。お父様はどのような仕事をしていたのですか?
平:
個人で経営コンサルタントとして働いていました。父のことは心から尊敬しています。幼い頃からさまざまな将来の選択肢を用意してくれたし、今でも人生の岐路に立つと父に毎回相談しています。
ニュージーランドの高校に進学した後は、英語漬けの日々でした。ホームシックになったりもして、ホームステイ先の自分の部屋でできる趣味はないかと考え、初めてプログラミングに接したんです。
Perlというプログラミング言語を用いて、CGIで小さなWebサービスを作っていました。2000年代初頭のことで、Googleは既にありましたが日本ではまだYahoo!が主流でした。

本田:
この頃はさすがに、まだSEOには取り組んでいなかったですよね?
平:
そうでもないんです。今回の企画に話を合わせるわけではなく、本当の話なんですが……(笑)。Webサイトを作っていくと、やっぱり誰かに見てほしくなるじゃないですか。当時はYahoo!カテゴリに登録してもらうのがすごく重要で、高校生ながら必死で申請して、3回目くらいで掲載されたんです。これが高校時代の一番の思い出でした。
本田:
すごい!Yahoo!カテゴリにサイトが登録されることは、当時のSEOでは必須の施策でした。まさか高校時代からそんなことをされていたとは。
平:
それが今の仕事につながっているわけですから、スティーブ・ジョブスの名言である「Connecting The Dots(点と点をつなぐ)」を感じますね。
事業成果に貢献することへの執着。Speeeとの出会いとCINC創業
本田:
大学は、アメリカ中西部・ワイオミング州のワイオミング大学 を選んだのですよね。日本人が選ぶ進学先としては珍しい気がします。
平:
MIT(マサチューセッツ工科大学)にも憧れましたが、学力的に難しく学費も高いのがネックでした。比較的治安がよく、自分の学力で入れて、かつ教育レベルもしっかりしている。その条件に当てはまったのがワイオミング大学だったんです。本田さんのおっしゃるとおり、ワイオミング州は日本人がほとんどいない、ザ・アメリカという感じの場所でした。
本田:
プロフィールでは大学を中退しているということですが。
平:
大学在学時の2009年頃、リーマンショックの影響がアメリカにも日本にも直撃しました。この状況で、高額な学費を出してもらうのはつらい。加えて、進級に必要な単位を落として留年が必要な状況になってしまいました。
このまま大学に通い続けていいのだろうかと父に相談して、一度社会に出て自分の地位を築いていこうと決断し退学しました。
本田:
帰国後はすぐに就職を?
平:
はい。ただ、求人がなくて就職活動は大変でした。自分のスキルが活かせるIT系に絞って応募しましたが、なかなか決まらず。最終的に、東京の広告代理店に就職することとなりました。
本田:
2009年というと、僕がゴリゴリSEOをやっていた頃です。出会えていれば絶対お誘いしたのに……(笑)。それにしても、プログラマーではなく広告運用からキャリアをスタートしたのですね。
平:
本音を言えばプログラマーとして働きたかったのですが、大学中退という学歴ですし、リーマンショック直後で選べる状況ではありませんでした。とにかくIT業界で100%の力を出し切ろうと思い、広告代理店で2年ほど働き、リスティング広告の運用に携わりました。
その後、当時の上司と一度会社を立ち上げたのですが、なかなかうまくいかず。改めて就職活動をする中で、SEOにフォーカスして探していたところ、SEOコンサルティングに取り組むSpeeeからラブコールをもらい入社が決まりました。同社ではコンサルティング部門のアナリシス、いわゆる分析を専門とするチームで働きました。

本田:
Speeeへの就職をきっかけに、SEOへどんどんハマっていったのですか?
平:
その通りです。Speeeで「事業としてSEOをやる」とはどういうことかを学びました。特に根拠を持って事業判断を下す文化や、徹底された数字管理には衝撃を受けたのを覚えています。
単に検索順位を上げるだけでなく、それをいかにお客様の事業の成果に結びつけるか。優秀な人材に囲まれながら、ビジネスとしてのSEOを叩き込まれました。Speee在籍中、本当に多くのことを学ばせていただきました。
本田:
そして、Speeeで後のCINC共同創業者となる石松友典さんと出会うのですね。
平:
私は入社したときから「将来起業したい」と公言していたのですが、それを聞いていた石松が「一緒にご飯行かない?」と誘ってくれました。そこで話すうちに、お互いにやりたいことの方向性が驚くほど一致していて。
そこから一気に仲が深まり、一緒に事業を立ち上げようという話になったんです。
本田:
CINCはビッグデータを活用したソリューション事業とアナリティクス事業を展開しているのが特徴ですよね。創業時、二人はCINCをどんな会社にしようと話していましたか?
平:
創業当初から石松と話していたのは、「お客様の事業成果に必ず貢献できることを大事にしよう」ということです。Webコンサルティングの中には、レポートを出して終わり、分析して終わりというケースが少なくありません。
CINCにご依頼いただいたからには、必ず「売上が上がった」と言われる会社にしたい。それが、すべてのサービス開発や組織づくりの軸になっています。
本田:
その思想から、あの有名なWebマーケティングの分析ツールの定番とも言える「Keywordmap」が生まれたわけですね。弊社が提供する「ミエルカ」の競合でもあるので、しっかりチェックしています(笑)。
平:
コンテンツマーケティング支援の中で、顧客ニーズを把握するための記事構成案を作る作業には膨大な時間がかかっていました。これを何とか機械化できないか、という課題意識が「Keywordmap」開発のスタート地点です。開発は私が中心となって行われました。
本田:
平さん自身の「ものづくり」の経験とSpeeeで培った「事業成果へのこだわり」が結実した結果、生まれたツールというわけですか。
平:
そうかもしれません。学んできたことが、初めて事業として形になったのがこのタイミングでした。当初は私一人で開発していたので、土日に1機能リリースするようなスピード感で仕事に取り組んでいました。365日、寝袋を会社に持ち込んで仕事に没頭していたこともあります。
その日々は大変でしたが、同時にとても楽しかった。遅れてきた社会人としての青春を謳歌している気分でした。
上場、そして退任。ものづくりの世界に飛び込む興奮を再び
本田:
スタートアップの熱い青春時代を経て、CINCは上場へと向かいます。これは創業当初からの目標だったのですか?
平:
最初から決めていたわけではありません。ありがたいことに、コンサルティング事業と「Keywordmap」事業が順調に伸びるのに合わせて、CINCの注目度も高まっていきました。そのタイミングが、経営陣として上場を意識し始めたきっかけです。
本田:
そこからの上場準備は大変だったと思いますが、平さんは何が一番つらかったですか?
平:
すべてが大変でしたが、一番はガバナンスの構築です。それまで社内のルールも規定も曖昧なまま急成長してきた組織に、上場企業としての規律を一気に浸透させなければならないわけですから。会社の雰囲気を変えて仕組みを整えていく過程は、私自身もメンバーも苦労した点だと思います。
本田:
平さんとしても、これまでやってきたこととは違うタスクに取り組む必要があったのでは?

平:
そうですね。事業計画の策定や投資家向けの資料作成など、プログラミングとは全く違うスキルが求められました。でも、会社とプロダクトの成長のためには不可欠だと信じて、日夜取り組んでいました。この頃は、かなりピリピリしていたと思います(笑)。
本田:
そして2021年10月、ついに上場を果たすわけですね。鐘を鳴らした瞬間、どんな気持ちでしたか?
平:
「ついにこの日が来たか」と。ずっと目標にしてきた瞬間だったので、本当に感動しました。厳しい準備期間からの解放感を覚えるのと同時に、ここからが本番だという引き締まる思いもありました。本当にいろんな気持ちが湧き上がってきましたね。
本田:
上場企業の経営者となってからは、どのような苦労や大変なことがありましたか?
平:
たくさんの場面で、「上場以前の自分はなんて未熟だったんだ」と感じさせられましたね。それを特に痛感したのはマネジメントでした。CINCを創業した20代なかばの私は、マネジメントの重要性や大変さをまったく理解していませんでした。
突然多くの部下を指揮する立場となってから、当時は自分の理想や正しさを優先し過ぎてしまい、メンバーの想いに十分寄り添えない場面もありました。今となってはとても反省しています。適切なマネジメントのあり方を体得するまで、多くの時間がかかりました。
その間、メンバーには迷惑をかけてしまったと思います。それでも、少しずつメンバーと対等な目線で話せるようになっていったのは、嬉しかったです。
本田:
私は平さんの近くで働いている人ともよく話すことがありますが、そこで聞かされるのは平さんのプロフェッショナル意識の高さです。普段はとても穏やかな平さんですが、仕事となると厳格な一面が飛び出すのでしょうね。
平:
仕事となると、お客様への提案は確実で完璧であってほしいと考えがちですね。お金をいただいている以上、ちゃんと価値を提供することは当たり前。だからもっとこだわろう。とはいえ、かつては表現が強すぎたと自覚しています。現在はメンバーと目線を合わせ、まず成果の意図を共有してからフィードバックするよう意識しています。
本田:
そんな日々を過ごした今年、10年以上務められたCINCを退任したわけですが、この決断の背景には何があったのですか?
平:
上場を果たして会社が第二創業期に入った中、経営者として求められる役割が少しずつ変わってきたというのが大きな理由です。
上場企業としては、組織を安定させて公の器として着実に会社を伸ばしていくことが求められます。一方で、私の根源的な欲求やケイパビリティは、やはり「ものづくり」にあるんです。特定のニーズに対してプロダクトを作り、お客様に提案して改善していくという、現場に対して強い想いがありました。
そのズレを感じながらも、経営者として何とかできないかと模索しました。しかし最終的には、もう一度CINCを創業した2014年のような、ゼロから何かを生み出す熱を感じたいという気持ちが強くなったんです。そのことを石松に相談し話し合った末、円満に退任を迎えました。

本田:
そして今、新たなチャレンジを始められているわけですね。
平:
現在は世界中で起こっているAIの波の中に、次のビジネスチャンスがないかを探している段階です。特に私はマーケティングでの経験が長いので、その知見を活かして最近話題のAIエージェント開発などに挑戦できないかと模索しています。
再び「つくる人」に戻って、ワクワクするようなものづくりをしていきたいですね。
たった一人で始めた「SEO研究チャンネル」の舞台裏
本田:
平さんといえば、登録者数1.8万人を誇る「SEO研究チャンネル」の存在も欠かせません。なぜ始めようと思ったのですか?
平:
チャンネルを開設したのが2020年頃で、コロナ禍のタイミングでした。
営業活動や展示会での活動が難しい中、自分たちの考えを発信する場を作りたいと思ったのが、最初のきっかけです。BtoB領域でYouTubeを始めるのはどうかとも思いましたが、悩むくらいならやっちゃえ!ということで、とりあえずチャンネルを開設しました。
チャンネルを始めるにあたり、石松にも相談して許可を取っています。とはいえ、あくまで個人のチャンネルということで、社員や外部の手は借りずに撮影から編集まですべて一人で制作することにしました。
本田:
すべて自分で!?私たちは全社総動員で取り組んでいるのに、すごいですね……。
平:
最近は外部の人に編集を手伝ってもらっていますけどね。
本田:
チャンネルを運営し始めて、どのあたりのタイミングから手応えを感じ始めましたか?
平:
再生回数が1動画当たり、大体2〜3週間で500ぐらいを上回り始めてからでしょうか。その頃から、営業先でお客様に「(動画を)観ています」と言われたとメンバーから聞くようになったんです。
本田:
「SEO研究チャンネル」といえば、Googleのコアアルゴリズムアップデートの分析動画が非常に有名で、多くのSEO担当者の指針になっています。これらの動画を作るために、どのような分析をしているのですか?
平:
ずっと大切にしているのは検索結果、すなわちSERPsです。SERPsをとにかく大量に見て、順位変動が起きたサイトと起きていないサイトを抽出しつつ、その差分をチェックする。そうやって、生のデータ=一次情報を見るようにしています。
本田:
大量のデータを見て判断していると。それをあれだけスピーディに行い動画化できるのは、平さんしかいないと感じます。その分析をもとに、お客様の支援を行っているSEOコンサルタントも多いのではないかと思います。

平:
私の動画の内容は完全にフリーコンテンツなので、ぜひ視聴者の皆さんは自由に活用してください(笑)。
AIはSEOを終わらせるのか?検索の未来で求められる人間の行動
本田:
平さんの目に、現在の生成AIの波はどのように映っていますか?
平:
デジタルマーケティング業界は、AIによって最も影響を受ける業界の一つでしょう。これまで多くの人材が必要だったクリエイティブを、AIでだいたいできるようになるかもしれない。そうなれば、我々コンテンツ制作者やSEOプランナーの働き方は大きく変わらざるを得ません。
人間がどういう立場に立つべきかは、ここ1〜2年でその答えが出てくる。そんな転換期にあると見ています。
本田:
どんな変化が起こるのか、私としては興味深く観察しているところです。具体的な点では、検索画面におけるAI Overviews(日本語名:AIによる概要)の影響などは顕著ですよね。
平:
私が分析している複数のサイトのサーチコンソールでも、はっきりと影響は出ています。流入数が大きく減少しているサイトは、間違いなくAI Overviewsの影響を受けています。
ただ重要なのは、クエリによって影響が全く異なるということです。あるディレクトリはガクンと落ちているのに、別のディレクトリはまったく影響がないというケースも珍しくありません。一概に「全サイトが危険だ」とは言い切れない状況です。
本田:
まだなんとも言えない状況が続いているのですね。AI検索からのサイト流入は、現時点で0.5%程度とされています。その一方、AEOやLLMO、GEOなど多くの言葉が生まれているように、AIとSEOとの関わりについての議論は盛んです。この点についてはどう思いますか?
平:
一つ言えることは、2010年代にスマートフォンが普及して大きく業界が変わったのと同様に、AIが大きなイノベーションを起こすということです。今後、AIは人間の検索行動や購買行動を大きく変えようとしています。我々マーケターは、この変化に柔軟に適応する必要があるでしょう。
SEOについても、これまで重要な評価指標だったトラフィックや検索順位とは異なる指標が生まれる可能性がある。その未来は、私としても全く予想できないですね。
本田:
昨今、いわゆる「SEOオワコン論」がささやかれていますが、これに対する平さんなりの反論はありますか?
平:
SEOオワコン論、もう何度目の話だろうというのが正直な感想です(笑)。引きのある言葉なので、私もYouTubeのサムネイルで使ったりしますが、実際は全く終わらないと考えています。
先日、SEOのプロフェッショナルであるランド・フィッシュキン氏が、「SEOは“Search Everywhere Optimization”だ」と提唱していました。この言葉は、まさに慧眼だと思います。
検索される場所がGoogleの検索窓に限定されず、あらゆる場所に拡大していく。それならば、SEOは終わるどころかむしろ進化していくと捉えています。

本田:
そんな変化の時代において、これからのSEO担当者にはどんなスキルが求められると思いますか?
平:
一つは、AIを使いこなす能力です。AIの仕組みを理解し、いかに自分の業務を効率化・高度化できるか。特に重要になるのが「問いの力」です。
ChatGPTに雑な指示をすれば雑な答えしか返ってこないように、AIの力を最大限に引き出すには、使い手の地頭の良さや、本当に欲しいものを的確に言語化する能力が求められます。AIの登場で、知識は平準化されるどころか、使いこなせる人とそうでない人の格差はむしろ広がっていくでしょう。
もう一つは、小手先のハックではない本質的な価値提供です。
AIはコンテンツの内容を人間のように深く読み込みます。良い評判があり、多くの人に言及される本当に価値のあるプロダクトやサービスを作ることが、結果的にあらゆる検索エンジンで評価されることにつながります。技術の発展が良い意味でハックを効きづらくしている。これは、マーケターにとって非常に良い状況だと言えるかもしれません。
SEOについて言うならば、極論これまでとやることはあまり変わらないというのが私の見解です。AI検索エンジンは、それぞれのAIモデルの学習内容からベストな情報を選択・表示します。つまり、その情報がさまざまなサイトで引用されていて、かつ良い評判であることが重要なのです。
これらは、昔からの広報やマーケティングで重視されていることと変わらないですよね。
本田:
真っ当なSEOやマーケティングに取り組むという、原点に愚直に取り組むことが、AI時代のマーケターには必要なのかもしれませんね。最後に、記事を読んでいる若手のマーケターに向けてメッセージをお願いします。
平:
今、SEOはAIによって大きな転換期を迎えています。フィーチャーフォンからスマートフォンへ移行した時期と同じくらい、大きなチャンスのタイミングです。あの時、Googleのアルゴリズムを極めれば事業を大きく伸ばせるという好機が生まれました。
AIによって仕事がなくなるといった、ネガティブな声も聞こえてきます。しかし多くの世論の関心を引いているということは、それだけAIに大きなインパクトがある証拠です。若手の皆さんは、私たちよりも頭が柔らかいはず。
今までの常識に囚われず、新しい技術や手法を恐れずに取り入れ、どんどん発信していってほしい。この変化の波を、ぜひチャンスとして掴んでください。

※写真はすべてWeWork神谷町トラストタワーにて撮影
🔶対談の全容は、ミエルカチャンネルで動画でもご覧いただけます。
普段のSEO研究チャンネルでは見られない、お父様への感謝を語る姿や、経営者としての葛藤を率直に話される姿に、平さんの誠実なお人柄が滲み出ています。「SEOは終わった」説への明快な反論も、データだけでなく平さんの温かい言葉で語られることで、より心に響くメッセージとなっています。ぜひ動画で平さんの素顔に触れてみてください。
関連記事
事例を探す






 この記事をシェア
この記事をシェア