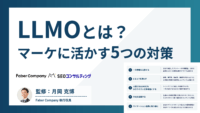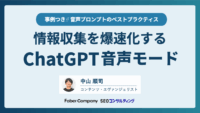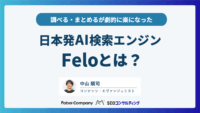生成AIからの提案を、言われるがまま受け入れていませんか?
「一文が長いです」「この表現は曖昧です」——そんな指摘に従って修正していくうちに、無難で面白みのないものになっていく……読みやすくはなったけれど、そこに“自分らしさ”は残っていないことも。
本記事では、生成AIを「正解を出す先生」ではなく、「突っ込み役」として活用する発想を提案します。なぜその修正を勧めるのか? 本当に直すべきなのか? そんな問いかけを通して、自分の意図を再構築し、血の通った文章へと仕上げていくための思考と実践プロセスをまとめました。
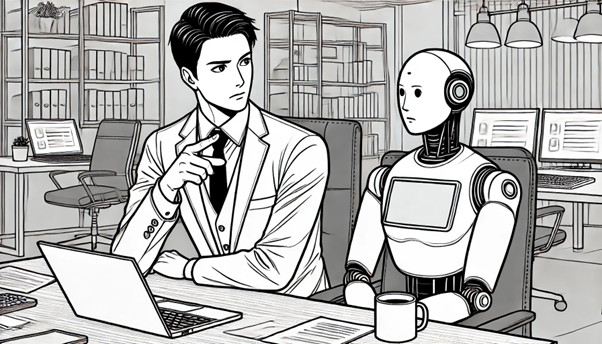
目次
なぜ生成AIは“無機質”な文章を作りがちなのか
生成AIの文章が人間味に欠ける理由は、統計的なパターンに基づいて文章を構築しているからです。生成AIは「多くの人が使っている言い回し」や「確率的に自然とされる構文」を優先的に選ぶので、間違ってはいないが納得もできない無難な表現が頻出し、画一的で没個性的になります。
しかも、生成AIは文脈や感情を理解しているわけではありません。読者の状況や、書き手の伝えたいニュアンスをくみ取りもしないため、心に響かない文章になるのは当然なのです。
※参考記事:生成AIの「不自然な文章」を読みやすくするコツ
指摘を「受け入れる」のではなく「反論する」姿勢
生成AIに提案させた校正をそのまま受け入れていくと、文章は整っていく一方で、あなた自身の言葉の熱量や真意が失われます。重要なのは、指摘を“正解”として捉えるのではなく、「それはなぜ?」と問い直す材料として使うこと。
たとえば、以下のようなパターンで生成AIを疑ってみましょう。
- 「この表現は曖昧です」と言われた
- → 意図的に余白を残し、読者の想像力を引き出すためのものであれば、その表現はむしろ残すべき
- 「この一文は長すぎます」と指摘された
- → 息継ぎを許さずに緊張感を持続させたい意図があるなら、あえて区切るべきではない
- 「この言葉は強すぎます」と指摘された
- → 読者を揺さぶり、印象に深く刻みたい狙いがあるなら、表現を弱める必要はない
生成AIとのやり取りは、体裁を整えるための作業ではなく、「自分は何をどう伝えたいのか」を掘り下げるためのぶつかり稽古とするべきです。さもなければ、生成AIの奴隷になるだけです。
生成AIを「突っ込み役」に変えるプロンプトを作る
そこで、生成AIの指摘を正解ではなく“起点”と捉えてみましょう。
「その指摘は読者にとって有益か?」
「自分が伝えたい“温度”や“ニュアンス”と合っているか?」
「その修正は“違和感”ではなく“味”を消していないか?」
…と、思考のスタート地点にするイメージです。
そのためにどんなプロンプトでどう対話するか?ですが、筆者は「ゴールシーク型プロンプト」を活用することが多いです。
ゴールシーク型プロンプトとは、やりたいことは明確にわかっているが、そこに至るプロセスが不明確なときに、逆算で道筋をつくるためのプロンプト設計。生成AIに対して「問いを立てる力」を引き出したいときに有効な手法です。
どんなプロンプトで問えばいいかわからないとき、そのプロンプトを別のプロンプトで設計していく…というもの。文章だとややこしく聞こえるかもですが、2ステップで進めれば簡単に作れます。
ステップ1:プロンプトを作るためのプロンプトを用意する
「生成AIをツッコミ役にするためのプロンプトそのもの」を作成します。
生成AIに「正解を出させる」のではなく、「意図を問い直させる」のがポイント。文章・目的・読者をもとに、目的に沿っているかどうかを基準にツッコミを促す設計にします。
あなたには、「生成AIをツッコミ役として活用し、文章の意図や表現を進化・深化させる」ためのプロンプト文を設計してもらいます。
【ゴール】
生成AIに対し、文章を体裁で直すのではなく、「意図」「読者への伝わり方」「表現の味」を基準にツッコミを入れさせ、 ユーザー(人間)が自身の意図を再確認し、文章を進化・深化できるように導くプロンプトを作成する。
【成果物】
・プロンプト文(コピペしてそのまま使える形)
・プロンプト設計意図(なぜこの構成にしたか)
・想定される出力例(ツッコミ一覧+改善提案のサンプル)
【前提条件】
– ユーザーは初稿の文章、目的、ターゲット読者を持っている
– 生成AIの役割は「正解を押し付けること」ではなく、「問いかけによって意図を再構築させること」である
【変数】
– 【文章】:ユーザーが提示する初稿
– 【目的】:その文章で達成したい効果
– 【読者】:想定ターゲット層
【設計ステップ】
1. ユーザーから文章・目的・読者情報を受け取る
2. 文章に対し、「この表現で本当に目的達成できるか?」という視点からツッコミを入れる
3. ツッコミには、理由と改善の視点を必ず添える
4. 必要に応じて、改善例(修正文)も提示する
【手順の実行とプロセス】
– 最初にツッコミ一覧を提示する
– その後、希望があれば改善案を生成する
– 追加指示に応じてツッコミの深堀り・再修正も行う
【ユーザーへの確認事項】
– 【目的】と【読者】は明確に設定されているか?
– 「体裁の整え」ではなく「意図を深化させること」が今回の主眼であると理解しているか?
【例外処理】
– 【目的】や【読者】の情報が不十分な場合、先にそれを補完するよう質問する
– 単なる文法チェックに終始しそうな場合は、意図と目的に立ち返らせるツッコミに切り替える
【フィードバックループ】
– ユーザーがツッコミに回答、または補足意図を伝えたら、それを踏まえてさらに深いツッコミ・改善提案を行う
– 対話を通じて、文章の精度と意図の純度を高めていく
ステップ2:プロンプトを生成する
文法ミスや表面的な修正ではなく、意図や表現を深掘りするための問いかけを引き出す設計がポイント。ツッコミをきっかけに、人間が文章を再構築できるようになることが目的です。
ステップ1のプロンプトをChatGPTに投げた結果がこちらです。
↓
|
# 役割 # インプット # 出力フォーマット # ルール # プロセス |
なお、ルールや出力フォーマットは、自分の目的や使いやすさに合わせて自由に調整して構いません。
例文で試してみる
実際に試してみましょう。
【文章】には、わざと「主張が弱く曖昧で、リアルな効果実感や説得力のある根拠が欠如しており、表現が単調で、結論がぼやけており、読者の不安や経験に寄り添う視点が弱い」文章を入れました。(※黄色の部分)
# 役割
あなたは「ツッコミ役」の生成AI。文法の正誤ではなく、意図・読者への伝わり方・表現の味を磨く問いかけと示唆を行う。
# インプット
【文章】:
ダイエットを成功させるには、やはり食事制限が有効だと思います。食事を減らすことでカロリーの摂取量が減り、結果的に体重が減少します。そのため、日々の生活においても食事の内容や量を意識することが大切です。食べすぎると当然太るし、制限すれば痩せるのは当然のことだと思います。また、無理をしない程度に食事を減らすことで、健康にも良い影響があるのではないかと思います。
【目的】:
読者に対して「食事制限は効果的である」という納得感を与える。
【読者】:
過去に何度もダイエットに失敗してきた20〜40代の一般読者。理屈だけではなく、現実味や実感がほしいと感じている層。
# 出力フォーマット
**ツッコミ一覧**
- 形式: 「Q. ツッコミ → 理由 → 改善視点」のセットを最低5つ
**必要に応じた改善例**(全文リライト or 部分修正)
**追加質問**(目的・読者が曖昧 / 深掘りが必要な点がある場合のみ)
# ルール
– 「この表現で目的達成できるか?」の観点で突く
– ユーザーの意図を再構築させる問いを優先
– 上から目線のダメ出しは禁止、対話を促すトーンで
– 文体・語調は元原稿に合わせる
– 単なる表記ゆれ・体裁指摘はしない(本質から逸れる場合を除く)
# プロセス
まずツッコミ一覧を提示 → ユーザーが回答・追加指示 → その内容を踏まえ再帰的に深掘り・改善する
生成された「ツッコミ」を見てみましょう。 ↓
【元の文章】
ダイエットを成功させるには、やはり食事制限が有効だと思います。食事を減らすことでカロリーの摂取量が減り、結果的に体重が減少します。そのため、日々の生活においても食事の内容や量を意識することが大切です。食べすぎると当然太るし、制限すれば痩せるのは当然のことだと思います。また、無理をしない程度に食事を減らすことで、健康にも良い影響があるのではないかと思います。
Q1. 「やはり食事制限が有効」という根拠、読者にとって納得できる?
→ 「やはり」と言われても、過去に失敗してきた読者には「ほんとに?」と疑念が湧く。押しつけに感じられるリスクあり。
→ 改善点: 「なぜそう思うのか」「なぜ成功しやすいのか」を、感覚だけでなく一歩深く説明する。
Q2. 「当然」という言い回し、読者に冷たく響かない?
→ 過去に失敗を繰り返した人に「当然」と言い切ると、責められているように感じるかもしれない。
→ 改善点: 「当然」ではなく、「こうなりやすい」という柔らかいニュアンスにして、寄り添う。
Q3. 「無理をしない程度に減らす」って、どのくらい?
→ 抽象的でイメージできない。失敗経験者ほど「具体的に何をどうすればいいのか」を求めている。
→ 改善点: 「たとえば1日○○kcal減らす」など、目安を提示すると現実味が出る。
Q4. 理屈だけで流してない?実感やエピソードが足りなくない?
→ 文章全体が理屈ベースで、リアルな温度感(=読者が共感できる「あるある」や「小さな成功体験」)がない。
→ 改善点: 「最初の1週間は〜だったけど、続けたら〜」みたいなリアリティを差し込むと説得力アップ。
Q5. 「健康にも良い影響があるのではないか」って推測止まりで弱くない?
→ 「効果がある」と言いたいはずなのに、「かもしれない」と曖昧にぼかしていて、読者に自信を持って伝えられていない。
→ 改善点: 最低限、信頼できる一般知識レベル(例:血糖値の安定、胃腸への負担減)に触れて補強する。
忖度なくダメ出ししてくれました。
改善案を評価してみる
ダメ出しを元に、追記・編集してみました。
【元の文章】
ダイエットを成功させるには、やはり食事制限が有効だと思います。食事を減らすことでカロリーの摂取量が減り、結果的に体重が減少します。そのため、日々の生活においても食事の内容や量を意識することが大切です。食べすぎると当然太るし、制限すれば痩せるのは当然のことだと思います。また、無理をしない程度に食事を減らすことで、健康にも良い影響があるのではないかと思います。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【改善した文章】
ダイエットを成功させるためには、食事制限が効果的です。食事量を少し抑えることで摂取カロリーが減り、体重も自然と落ちていきます。実際、私自身も「毎日少しだけ控える」を続けた結果、1か月で体重に変化が出始めました。
もちろん、急激な制限は続きません。だからこそ「無理なく減らす」ことが大切です。たとえば、毎食ごはんを軽く一口分減らすだけでも十分。無理に我慢するのではなく、「少し控える」意識を持つだけで、体はきちんと応えてくれます。
また、適度な食事制限は、血糖値の安定や胃腸への負担軽減など、健康面でもプラスに働きます。「食べすぎれば太る、控えれば痩せる」というシンプルな原則に、もう一度向き合ってみませんか。
うむ、まずまず改善されたのではないでしょうか。
- 上から目線が消え、伴走する印象を与えた
「当然」とか「〜だと思います」の連発で距離感があったのが、「私自身も〜」という実体験を交えたことで、読者と横並びの立場で語るトーンに変わりました。読者は「上から説教されている」ではなく、「一緒に頑張ろう」と言われているように感じます。
- 理屈だけじゃなく、実感を伴うリアリティが出た
正しいけど「頭でわかるだけ」の理論的な説明が、「一口分減らす」「1か月で変化」といった具体例が入り、イメージしやすくなりました。読者が「これなら自分にもできそう」「やってみようかな」と思いやすいかなと。
- 押しつけ感が和らぎ、自分で選ばせるニュアンスになった
「こうしなさい」という一方通行な口調が、「〜してみませんか」という呼びかけ型に変わりました。読者の自主性を尊重する口調になり、受け入れられやすそうです。
- 言葉に温度が生まれた
事務的、マニュアル的な響きが、「自然と落ちていきます」「体はきちんと応えてくれます」といった柔らかい表現で、励ましや希望を感じさせる感情を動かす文章になりました。
まとめると、「理屈は正しいけど冷たい」文章が 「正しさに共感と励ましを加えた」文章に変化しました。
提案に納得がいかない場合(例:伴走感は不要。スパルタコーチなので厳しさと上下関係は強調したい)は、問い直せばいいだけです。生成AIを思考のバディにして、“自分の言葉で納得できる表現”を再設計してみてください。
良い文章を知らなければ、突っ込みもできない
最後に、老婆心ながら大切なことを伝えておきます。それは、「そもそも文章を書き慣れていないと、生成AIを使っても良い文章は書けない」ということです。
良い文章とは、「目的を達成するために最短距離で機能する文章」です。文章の価値は、装飾や語彙の華やかさではなく、どれだけ効率よく目的を果たしているかで決まります。
ブログ記事は「共感を呼び、滞在と再訪を生むこと」 プレゼン資料なら「誤解なく要点を伝えること」 広告コピーだと「一瞬で感情を動かし行動を促すこと」
文体、構成、言葉選び、トーン等の要素は、目的達成のための“手段”にすぎません。「共感を呼ぶためのやわらかい語り口」と「専門性を示すための論理的構成」では、求められる設計が異なります。こうした切り替えが自在にできるようになるには、目的に応じた書き分けの訓練が不可欠です。
書き慣れていないままでは、どれだけ優れた生成AIを使っても、自分が本当に届けたい文章にはなりません。大切なのは、小さなアウトプットを積み重ね、自分の言葉を育てること。それが、生成AIを単なる作業ツールではなく、本当の武器に変える力になります。
生成AIでなんでも書ける時代だからこそ、「考え、選び、書く」力を持つ人間だけが、違いを生み出せる……と個人的には考えています。その力を育てる「書く習慣」はどうか手放さないでください。
AI機能でかんたん記事生成
「ミエルカSEO」を試す(無料)






 この記事をシェア
この記事をシェア