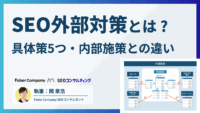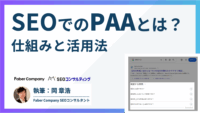2025年10月28日~29日の2日間、東京都千代田区にて開催された、DemandMarkets株式会社主催のFOUND Conference Tokyo 2025に、当社のFaber Company Founder室長 本田卓也、SEOスペシャリスト 小丸広海、プロダクトマネージャー 市川莉緒、ディレクター 高田愛が参加、登壇してきました。
国内外から検索マーケティングのエキスパートが終結し、会場は大盛り上がり!その様子をたっぷりお届けします!(筆者:高田)

▼Day1の様子はこちら▼
「FOUND Conference」は、世界的に著名なRand Fishkin(ランド・フィシュキン)氏、Lily Ray(リリー・レイ)氏、Mike King(マイク・キング)氏なども参加した、国内では初のグローバル検索マーケティングカンファレンスです。SEOはもちろん、検索広告、コンテンツマーケティング、AI活用、データ分析など、多岐にわたるテーマについて、国境を超えた活発な意見交換が行われました。
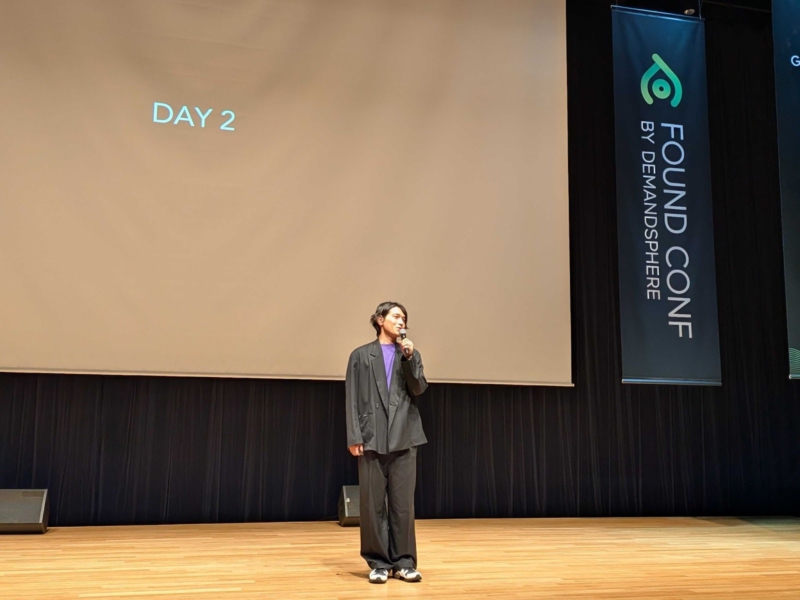
セッション① AIサーチ・プレイブック
Day1はお昼過ぎからのスタートでしたが、Day2は朝10:00からセッション開始。一発目は、あの有名なMike King(マイク・キング)氏のセッションです!

マイク・キング
Founder of iPullRank, USA Today Top 10 SEO
マイクの愛称で知られるマイケル・キング氏は、デジタルマーケティングエージェンシー iPullRank のCEO兼創業者であり、テクニカルSEO、コンテンツ戦略、機械学習、そして「関連性エンジニアリング(r17g)」と呼ばれる新領域を専門としています。関連性エンジニアリングは、検索プラットフォームにおけるブランドとオーディエンスの関わり方を再定義するもので、マイケル氏はその第一人者として、SEOをキーワード中心の発想から「関連性」重視のデータ主導・AI駆動型アプローチへと進化させてきました。これまでにSAP、American Express、Nordstrom、SanDisk、General Mills、FTDなど、世界的な大手から中堅企業まで幅広いブランドを支援。検索とAIの融合分野におけるリーダーとしても知られ、生成AIスタートアップへのプロンプトエンジニアリング支援や、企業のAI検索・コンテンツ戦略適応に関するコンサルティングを行っています。コンピュータサイエンスの知識に加え、インディペンデントのヒップホップアーティストとしての経歴も持つ彼は、テクノロジーとクリエイティブを融合させて現代のマーケティング課題に挑んでいます。2025年にはニューヨークで新カンファレンス「SEO Week」を立ち上げ、r19gをSEOの次なる進化として提示。また、SEOの基本原則と関連性エンジニアリングをつなぐ包括的ガイド『The Science of SEO』の出版も予定しています。
(引用:AIサーチ・プレイブック by マイク・キング- FOUND Conf)
・SEOだけにとどまらず(ラップ、音楽…)など多才な来歴を紹介
・歴史的にユーザーが莫大な情報を得られる時代である
・訪問したページなどのユーザー情報は、Googleのエコシステムによってパーソナライズに使われている
・ユーザーの行動が変化しており、より多くのプラットフォームを使うようになってきている。もちろんGoogleが1番大きい
・データソースも変化している、サーチはブランディングチャネルになってきている
・テキスト、Googleレンズ、Google liveなどの多くの検索があり、デジタルと現実世界のフリクションをなくす方向にきている
・AI Overviewsによりクリック率定価、Wikipediaも下降トレンド。SEOは死んだのだろうか?
・Googleの各所での発言は、クリック数は減るもののより質のいいトラフィックになることを示唆
・クリックが減ってLLMトラフィックが重要になるならばGEOは重要になるのか?
・GEOの呼称が定着してきてはいるが、様々な呼称による議論で我々は時間を無駄に使った
・我々は、実際には“検索エンジンに最適化”しているわけではなく、検索エンジンが理解しやすいように情報を設計(feature engineering)している
・Relevance Engineeringは、Artificial Intelligence(人工知能)、Content Strategy(コンテンツ戦略)、User Experience(ユーザー体験)、Information Retrieval(情報検索学)、Digital PR(デジタルPR)を融合させた先にある
・コーディングなどはAIに任せられるので、新しいスキルが必要になってきている
・ベストプラクティスはもう使えなくなってきている。より多くのことをしてもより多くの結果は得られない
・GEOの担当者を雇いたがる傾向もあるが、SEO担当者から見たら無意味
・AIは素早く返答してくれるので、ユーザーの手間を減らす
・ユーザーが求めるものも変化してきている。10本のリンクの羅列ではなく文脈を捉えた答えを求めている
・検索はブランディングのチャネルでもある
・AIからきたトラフィックはCVが高いと言われているが、分母が少ないことも考慮する必要がある。
・AIはさらに利用が増えていくことが予測できる。ユーザーが使うプラットフォームも増えていくだろう。だが結局はGoogleが勝つと言われている。なぜならGoogleは誰よりもデータを持っているから
・多くのコンテンツがAIでつくられている(AIスロップ)
・生成AIの盗用は、当初検知が容易と言われていたが、Googleが検知できているとは思えない
・ハルシネーションも大きな問題。AIで生成させたものは60%の割合で間違っているという検証結果もある
・LLMを使った記事でもいい結果を出すことができるなら、我々の仕事も変わっていく
・検索モデルの進化、レキシカルモデル(キーワードの有無/分布)、セマンティックモデル(意味の理解)、ハイブリッドモデル(両方の組みあわせ)
る
・AI Modeはより多くのクエリを追いかけているので、多少時間がかかる
・AI側としては、コンテンツの抽出になるべくリソース・お金をかけたくない
・構造的に抽出しやすいコンテンツにすべき
・スコープの明瞭さが大切になる、情報をアップデートしていくことも必要
・データドリブンの重要度が増している
・ブランドインプレッションを増やし、潜在的にユーザーの選択に含まれるようにすべき
・主語、述語、目的語をしっかりさせた文章の方が拾いやすい。曖昧性を避けることが重要
・我々の作業を助けるツールは沢山ある。活用していこう
・ユーザー行動が変わってきている以上、SEOを超える対応が必要になってきている、Visibilityを高めることが重要
セッション② SERP Analytics 2.0
2日目の午前中は、海外のトップSEO playerのセッションが続きます。2人目は今回の主催・DemandMarketsのFounderでありCEOのRay Grieselhuber(レイ・グリセルフーバー)氏です。
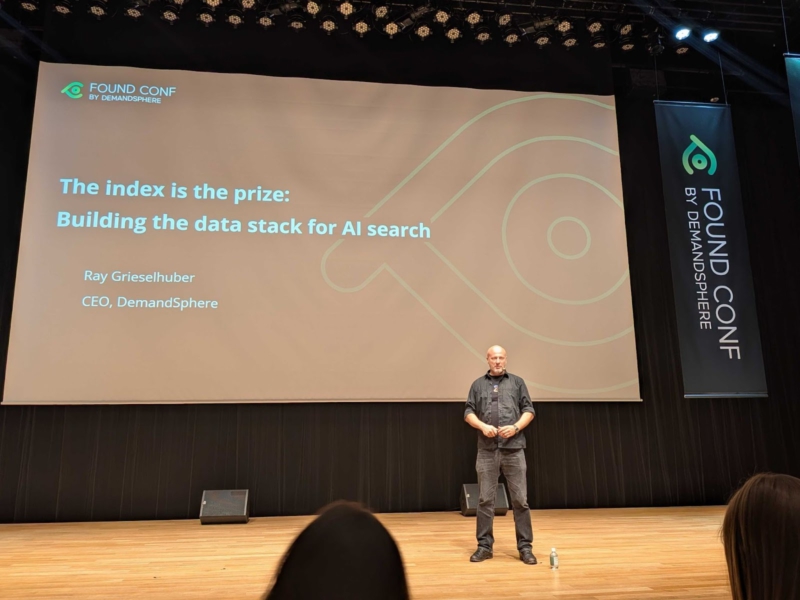
レイ・グリセルフーバー
DemandMarkets株式会社 CEO & Founder
検索およびデジタルマーケティング分野で10年以上にわたり活動。サンディエゴに拠点を置くCovario社で、業界初のエンタープライズ向けSEOプラットフォームの主任アーキテクトを務めたのち、2010年夏にY Combinatorに参加。SEOとコンテンツマーケティングを通じて企業が顧客と本物のつながりを築けるよう支援することを目的に、GinzaMetricsを立ち上げる。その後プラットフォーム開発者として、また業界のアドバイザーやビジョナリーとして、ブランドや代理店のオンラインでの発見性を高める支援を行う。ad:tech Tokyo、PR Summit、FOUND Conference SV、FOUND Conf NYC、DATA Conference、Media Finance Summit、LeadsCon NY(2012年8月)、PubCon、Under the Radar Conference、そしてY Combinator Ad Innovation Conferenceなど、数多くの業界イベントで講演している。
(引用:About Us – DemandSphere、翻訳は筆者)
・LLMからのトラフィックは伸びているが少ない(ほぼ1%以下)
・”SEO is dead” vs “It’s all SEO”は無意味なディベート。Googleも含めた全てがAI検索だといえる
・結局はユーザーエクスペリエンスが全て
・LLMのトークンが予測できる範囲には制限がある
・インターネットのコンテンツを全てLLMに入れるというのは物理的に不可能なので、RAGは必要不可欠
・インデックスがどこからきているものなのかが重要。Open AIはGoogleもBingも利用している
・検索エンジンそのものがAIの成功例
・1万プロンプトでChatGPTの引用を比較したら、検索結果との重複率はGoogleが半分以上、Bingは15%くらいだった
・AI Modeがローンチされ、クエリファンアウトの話が注目されたが、ChatGPTもクエリファンアウト(同様の仕組み)を利用している
・Googleは10年前くらいからAI検索の技術を進めてきた
・人間のアテンションが一番大事
・AIモデルのレスポンスを理解する必要がある
・エンティティが変化した時にトラッキングできないのでブランドメンションは必要
・LLMからのトラフィックを見るためにリファラルデータも必要
・ログ解析は、ログそのものを取得するのに多くのハードルがあり、さらにその解析も難しかったが、AIが話題になっている今、経営レベルで必要だという判断がされるようになり、取得・解析の障壁がさがった
・プロンプトリサーチは難しい。ChatGPTから提供されるデータもないし、キーワードだけの分析ではうまくいかないことがSEOの歴史からも見えている
・Share of VoiceがAI分析やSEOのKPIとしてよく使われてきている
・データに対して疑問を持ち、データを合わせたところでインサイトが得られるかどうかが重要
ランチ&サブステージ 生成AI時代の検索とマーケティングの未来像
大物2人のセッションを終えて、ランチの時間です。
サブステージとして、電通デジタルの地元 昇太氏、四本松 太郎氏、稲垣 昌輝氏のセッションがありました。
※ランチタイムに行われたこともあり、本ステージはお写真だけで失礼します。みなさんお昼を食べつつも熱心に聞かれており、注目度の高い内容でした!

地元 昇太
株式会社 電通デジタル AIイノベーション事業部プロデュースグループ グループマネージャー
電通入社以降、テレビを中心としたメディアプランニングをはじめ、映画/ドラマの出資やタイアップ、放送外収益となるような新規ビジネスの立ち上げなど放送ビジネスに関わる業務を幅広く経験。2024年より電通デジタルに出向。各種生成AI案件の提案やデリバリー、新規サービスの立ち上げから開発リードまで幅広く従事。 産学連携の一環として東京大学との共同研究も行い、国際学会で発表するなどアカデミック面でも精力的に活動中。
四本松 太郎
株式会社 電通デジタル オウンドメディア第2事業部SEOグループ グループマネージャー
電通デジタルでSEOコンサルティング支援するグループの責任者として、様々なタイプのWebサイトのグロース支援を行う。直近では生成AI向けの分析ソリューションなどの開発に参画。 広告やWeb開発、膨大データの分析等、SEO周辺領域のナレッジを活かし、マーケティング視点でのSEOコンサルティングを推進する。
稲垣 昌輝
株式会社 電通デジタル オウンドメディア第2事業部SEOグループ シニアSEOストラテジスト
シニアSEOストラテジストとして、難易度の高いYMYL領域や大規模DBサイト、大規模ECサイトのSEOコンサルティング支援を担当。 集客にとどまらないユーザー体験/コンバージョン最適化を前提とした設計を得意とする。 現在は、AI時代のコンテンツの在り方についても、最新の調査データに基づいたコンサルティング支援を提供。
(引用:生成AI時代の検索とマーケティングの未来像 by 電通デジタル – FOUND Conf)
セッション③ Search Synthesis:広告とSEOのプロに聞く AI 時代の検索
午後は、齊藤 麻子氏(LIG)、杉原 剛氏(アタラ)、渡辺 隆広氏(DMM.com)によるセッションからスタート。

齊藤 麻子(写真左)
株式会社 LIG LIGブログ編集長
1992年生まれ。2014年九州大学芸術工学部卒業後に採用コンサルティング会社へ新卒入社。法人営業から新規事業推進、マーケティング業務に従事したのち、2018年にLIGへ。2023年にLIGブログ編集長、2024年に人事部長に就任し、現在は自社のマーケティング・人事業務を担う。副業ではライターとして活動中。あだ名は「まこりーぬ」。著書『デジタルマーケの成果を最大化するWebライティング』(日本実業出版社)
杉原 剛(写真右)
アタラ株式会社 代表取締役 CEO
アタラ株式会社 創業者兼代表取締役CEO。慶應義塾大学 法学部法律学科卒業後、KDDI、インテルを経て、オーバーチュア(現Yahoo!検索広告)、Google日本法人で広告営業戦略を担当。2009年にマーケティングのコンサルティングサービスやツールを提供するアタラを創業。プラットフォーム広告、リテールメディアなどの最新情報を発信する、日本では数少ないプラットフォームビジネスアナリストでもある。「プラットフォームの思考回路」チャンネルをX、LinkedIn、Voicyで運営。
渡辺 隆広(写真中央)
合同会社DMM.com SEOマネージャー
SEO専門家。1997年に日本で初めてSEO事業を開始して以来、国内外のさまざまな企業のSEO推進を支援。エンタープライズSEO、コンテンツマーケティング、UX/UIを得意とする。業界歴29年の第一人者として多くの執筆・講演活動で活躍中。主な著書に「検索にガンガンヒットさせるSEOの教科書」「Googleコアアップデートの読み解き方」など。
(引用:Search Synthesis:広告とSEOのプロに聞く AI 時代の検索 – FOUND Conf)
渡辺さんとの問答
・検索利用者の立場とSEO含むマーケターの立場、それぞれでAI検索によって変化が起こっている
・検索技術と検索行動は相互に影響しながら発展してきた
・検索の用途が広がれば検索する人も増える、これまでも用途の広がりとともにユーザーが増えてきた
・検索利用者の立場から考えると、AIによって検索はシュリンクするわけではなくむしろ広がると予想できる
・一方でマーケターにとっては、今まで欲しいと思っていたデータがAIによって瞬時に手に入るので、分析や考える時間が増えると考えられる(例えばコードを書きたいと思った時、以前はサンプルを検索して探し、どこを変えればいいか調べてから書いていたが、今はAIで瞬時に生成されるため、そのコードを用いた分析や考察により時間をかけるようになる)
・AI検索に関しては、正直「煽りすぎ」だと考えている
・SEOがもし変わるのであれば、検索のルールが根底から覆された時か、Googleでない検索エンジン(あるいは検索エンジンを代替するもの)が覇権を握った時
・渡辺さんが経験している限り、2010年以降、2年に1回のペースでSEOが死んでいる、SEOが死んでいると言っている人々は自分たちが持っているテクニックが使えなくなったからそう言っているだけ、SEOを何のためにやっているのか、というビジネス軸で考えたら、やることはこれまでと変わらない
杉原さんとの問との問答
・Googleは今何を考えどんな戦略をとっていくのか?
・Googleは2023年のBard(Geminiの旧名称)のプロモーションが上手くいかず、不信感を与えたがその後立ち直っている
・Googleの動きを考える際には、Googleの性質(強烈なユーザーファースト)と収益性(広告という情報を後付けすること)から考えることが大切
・杉原さんからみてGoogleは、AI事業に関してはユーザーファーストに立ち戻っているように見える。かつ収益化にも成功している
・ある程度うまくいっている基幹ビジネスにメスを入れるのは難しいことだが、Googleは基幹ビジネスであるAI事業で大手術を行い、大きく成長させることに成功した
・Googleは今のところ怖いものなしな状況、訴訟も抱えてはいるが今のところ無傷
・CPCが上がり、オーガニックが減っている中で、検索広告の予算を増やしている企業も多い。今はとにかく情報を注視していく必要がある。
・ChatGPT内での広告は、来年くらいに始まるのではないかと予想している、ChatGPTは巨額の投資を受けているので、返済のために広告をやらざるを得ない
・ChatGPT内の広告が始まったら、すぐにテストするべき
・検索を仕事にする上で変わらないものは何か?
渡辺さん↓
・目先のテクニックはなくなる(たとえば外部リンクは当時とくらべてやっている人はほぼいない)
・SEOは市場と事業とユーザーを理解することから始まる、その3つを理解しないと自分が何をすべきかわからないままになってしまう
杉原さん↓
・広告を含むほとんどがAIで大部分が自動化されているが、人が意図を持って情報を探していくことは変わらない。これからも人間がユーザー行動の深読み・裏よみをしていく必要はある
セッション④ 事業会社のSEO担当者が語る:AI時代のリアルな現場と意思決定
次は、酒井 亮平氏(リクルート)、そして主催のDemandMarketsのジャパンカントリーマネージャーである室屋 武尊氏によるセッションです。

酒井 亮平(写真左)
シニアマーケティングリード
1984年生まれ。大学を卒業後、SEOコンサルティング会社等を経て、株式会社リクルートライフスタイル(現:株式会社リクルート)に中途入社。SEOスペシャリストとして6年勤務後、スタートアップ2社でメディアグロースを経験。2020年に復職し、現在はマーケティング室SEOチームのリーダーとして、ライフスタイル領域やライフイベント領域、SaaS領域のSEO組織の構築・強化を指揮。プレイヤーとしても活動し、事業アセットを活用した競争優位性を築くためのSEO施策を多数推進。SEOを軸足とした新規性・汎用性の高いマーケティング施策を創出しつづけるための仕組みづくりに挑戦している。
(引用:事業会社のSEO担当者が語る:AI時代のリアルな現場と意思決定 – FOUND Conf)
室屋武尊(写真右)
DemandMarkets株式会社 ジャパンカントリーマネージャー
グローバル企業を中心にデジタルマーケティングをリード。英国ユニコーン企業Farfetchでは、 シニアマーケターとして日本におけるSEOを中心としたグロースに従事。LVMHグループを経て、2019年DemandSphereに参画。2020年にジャパンカントリーマネージャーに就任。
(参照:【プレスリリース】オーガニックマーケティングソリューションの『DemandSphere』、日本カントリーマネージャーに室屋武尊の選任を発表 – DemandSphere)
・酒井さんは、大規模サイトの内部リンクが検索順位の改善に寄与するかどうか、といった実験・検証も行っている(無限の組み合わせが可能な内部リンク施策において、どの組み合わせでリンクを送ったらいいのか、ECのような大規模サイトでは出品者の状況などによって日々変わるので、それをデータサイエンティストと協力してアルゴリズム化したりしている)
・AIの出現によってROIが合わなかったSEO施策ができるようになった。例えば、フリーワード検索のタイトルについて、単語の意味合いを理解した上でより自然にタイトルを最適化させることも可能になった
・現段階ではAIからのトラフィックは5%もない。しかし伸びていることは事実で集客チャネルとしても活用が期待されているが、今後の影響度は予測がつかない
・生成AI施策も不明点が多いので、何もしないのもリスクである一方で、無批判な投資もリスク。そこで、データにもとづいた意思決定が重要になってくる
・逆にROI的にできることは限られるので、データに基づいてROIの説明がつきそうなスコープで検証を進める
・その説明をするためにも、モニタリング環境を整備することが必要
・役員をはじめとした経営者に「渡辺さんが言っているんで大丈夫です」「マイクキングが言ってるので大丈夫です」では通じない、ちゃんとデータをみて現在時点がどこなのかを確認していく必要がある
・例えば、この割合までAI検索流入が増えたらこういう施策をとる、というAI流入対応を本格化するラインをひく
・AI活用の意思決定方法はAI以前から変わっていない。昔も今も、SEO担当者は、戦略から実行までデータドリブンな意思決定が期待されている(採用の募集要項からも読み取れる)
・マーケティング担当者が経営レベルでどういう意思決定がされているのかを見に行かないと、マーケティング担当者の預かり知らぬところで「なんかイケてるから」という投資判断・事業判断がされる恐れもある。データを持っているからこそ現場メンバーが判断していくことが重要
セッション⑤ 「選ばれるブランド」の羅針盤:Instagram広告による検索リフト事例とLLMOで加速する指名検索の次世代PR戦略
次はオプトの黒沢 槙平氏、野嶋 友博氏、SPRIXの鵜沢 修平、Metaの水谷 晃毅氏、LANYの竹内 渓太氏によるセッション。

黒沢 槙平(写真左端)
株式会社 オプト 広告領域 上級執行役員 SVP
2010年㈱オプトに入社。人材・教育業界を中心とした広告運用オペレーションからコンサルタントまで従事。2016年に広告運用コンサルティング部の部長を経て、2019年デジタルマーケターの人材開発の専門部署を立ち上げ、責任者に就任。その後、人事部部長の兼任を経て、2021年1月より、コーポレート領域(人事・経営企画)管掌の執行役員に就任。2024年4月より広告運用管掌の執行役員:VP、2025年より広告領域 上級執行役員:SVPに就任し、広告事業全体の戦略策定・実行の責任を担う。
野嶋 友博(写真左から2人目)
株式会社 オプト 広告領域 プラットフォームサクセス本部 専門役員
2015年株式会社オプトに入社。SNSを中心とした広告運用に携わる。
2021年より、営業および広告運用組織の部長に就任し、EC・教育・人材業界をはじめとするクライアントを担当。日本で9名のみ認定されている、LINEの認定講師「LINE Frontliner」に認定。2022年より、戦略・戦術プランニング組織を立ち上げた後、2025年1月より、プラットフォームサクセス本部専門役員に就任。
鵜沢 修平(写真中央)
株式会社スプリックス 執行役員 株式会社湘南ゼミナール 取締役 株式会社Edutainment-Lab 代表取締役
2010年、株式会社ベネッセコーポレーションに入社。toCのマーケティング業務や事業開発に従事。その後、株式会社博報堂にて、様々な業種・企業のブランド戦略、コミュニケーション立案、新しいテクノロジーを活用したサービス開発に従事。現在は株式会社スプリックスにて、コーポレート及び各サービスブランドのマーケティングを管掌。2024年に株式会社湘南ゼミナールの取締役に就任。2025年にスプリックスとBrave groupとのJVである株式会社Edutainment-Labを設立し、代表取締役に就任。
水谷 晃毅(写真右から2番目)
Meta日本法人 Facebook Japan 営業部長
外資系コンサルティング会社にて戦略コンサルタントとして勤務し、消費財や飲料、スポーツブランド等のクライアントを担当。テーマとしては中期経営計画の策定、新規事業開発、マーケティング改革、BPRなど、戦略立案から変革推進まで従事。2017年Facebook Japan入社。広告代理店との事業開発やパートナーシップを推進。現在は営業部長として、同社のデジタル代理店チームを統括。
竹内 渓太(写真右端)
株式会社 LANY 代表取締役 CEO
株式会社リクルートホールディングスにデジタルマーケティング職で新卒入社。3年間デジタルマーケティングに従事。大規模サイトのSEOを中心に、デジタル広告運用やB2Bマーケティングなど多種多様な業務を経験。その後、株式会社LANYを創業し、Webメディア・サービスサイト・データベース型サイトなど幅広いモデルのSEO改善をプレイヤーとしてサポート。現在もプレイヤーとして多くの企業のSEOコンサルティングに取り組んでいる。著書『強いSEO』『強いBtoBマーケティング』などを出版。
(引用:「選ばれるブランド」の羅針盤:Instagram広告による検索リフト事例とLLMOで加速する指名検索の次世代PR戦略 – FOUND Conf)
・指名検索をいかにのばすか?(メインテーマ)
・指名検索は、マーケティングのROIが高く、ブランドの強さを示す指標でもあり、AIによる検索行動の変化などからも重要視されている
・Instagramが指名検索に効いていた森塾の事例を紹介。森塾を経営するスプリックスは指名検索数をKPIにしている、指名検索のCV数は5年で1.6倍で増加。教室が増えるごとに指名検索は増えるべきだと考えている
・CPAもCPCも上がっている現在、指名検索の重要性はましている
・指名検索の評価はロジックが複雑でやりづらいので、評価顧客に直接声を聞いたり、サンクスページで広告のクリエイティブを見せて「どの広告を見たことがありますか?」というアンケートをとっている
・見たことがある広告クリエイティブを答えてもらうアンケートは、流入チャネルと紐付けてどんなクリエイティブが効いていたのかを調査できるのがメリット
・AIでフリー回答を集計したところInstagramが圧倒的に多かった(助成想起ではなく純粋想起なので有効である可能性は高い)
・Instagramは、「好きと欲しいをつなぐプラットフォーム」と考えている。実際、Meta広告によるサーチ経由流入の平均的なリフト率は約9%
・指名検索貢献CVも含めた費用対効果算出と予算アロケーションを実施することで、認知獲得の予算をCV獲得に移行していく動きも出てきている。オフラインを含めて指名検索価値を可視化することが重要
・目に見えないプロセスがAIの普及によって複雑化・ブラックボックス化している
・AIの調査に人間が納得してCVする場合、サイト訪問はスキップされる可能性がある→今後はAI検索も意識して対応していく必要がある
・RAGの影響が大きそう。比較サイトが多く掲載されていたり、KWにマッチした口コミが用意されていたりすることが影響している可能性あり
・森塾が意識してAIに最適化しているかというとしていない。ブランディングの一環としてサービスのコンセプトを研ぎ澄ませられるかどうかがポイント
セッション⑥ AIと共に進化するウェブ検索。BingとCopilotが切り拓くデジタル広告の未来
ここでまさかのBingが登場!日本マイクロソフトの有園 雄一氏が、BingとCopilotについて語りました。
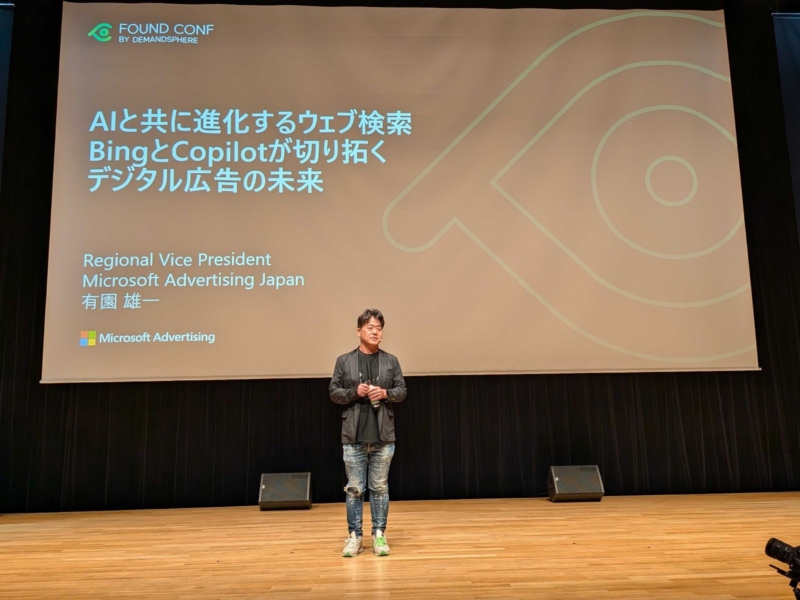
有園 雄一
Regional Vice President, Microsoft Advertising Japan
早稲田大学政治経済学部卒。 1995年、学部生時代に執筆した「貨幣の複数性」(卒業論文)が「現代思想」(青土社 1995年9月 貨幣とナショナリズム<特集>)で出版される。2004年、日本初のマス連動施策を考案。オーバーチュア株式会社(現ヤフー株式会社)、グーグル株式会社(SalesStrategy and Planning/戦略企画担当)、アタラ合同会社COOなどを経て現職。2004年、検索キーワード入りテレビCMを考案、日本で最初にトヨタ自動車「イスト」CMが採用。2014年、Dual AISAS Model®を提唱。株式会社テレビ朝日の番組「#モデる 」では番組企画を支援し、DualAISAS Model®️を利用して、「テレビ番組-テレビCM-SNS-ウェブサイト-EC/店舗」の連携を意図したコミュニケーション設計を行う。2016年~現在、zonari合同会社 代表執行役社長。2016年~19年、株式会社電通デジタル客員エグゼクティブコンサルタント。2018年、アタラ合同会社フェローに就任。2018年度 株式会社電通 電通総研 カウンセル兼フェロー。2020~2021年、株式会社ビービット マーケティング責任者。2019年~2022年、電通総研パートナー・プロデューサー。2022年8月~現職
(引用:AIと共に進化するウェブ検索。BingとCopilotが切り拓くデジタル広告の未来 by Microsoft Advertising Japan – FOUND Conf)
・CopilotはWindowsとつながっているので広告を配信できるユニークユーザー数は結構多い
・実は英語圏を中心にBing、Copilotのシェアは増えている
・CopilotはWindowsに組み込まれている機能があるので知らないうちに使っていることも
・ChatGPTでできることはCopilotでもできる、しかも全部無料
・PowerPointなどのMicrosoft製品とCopilotの統合は進んでいる
・EC系は強い、転職、人材、旅行など検討時間が長いものはPCで調べる人も多い、そこにCopilotがアプローチしやすいという現状がある
・Windowsのすべてのプロダクトには基本Copilotが実装されていてユーザーと対話しながらサポート
・ChatGPTが使われるほどに Copilotをトレーニングし Microsoftでより便利に使えるようになるサイクル
・BingのインデックスはChatGPTに提供されている
・Shopping機能などは英語圏で人気になりつつある
・Copilotを利用するユーザーは平均して収入や教育レベル(学歴)が高い傾向にある
・若年層ユーザーを重要視している
・音声入力アクティブユーザーが増えているのも若年層ユーザーの影響か
・会話型、エージェント、パーソナライズ、とエクスペリエンスは新たな時代に
・仕様上ファーストパーティデータのターゲティングの精度が高い
・Googleインポートを連携してMicrosoft広告をつかえるので時間と労力を削減できる
・1社独占の状態は好ましくないスタンス
ブレイク&サブステージ ページのEEATを高める方法について
一旦休憩時間。とはいえ、ここでもサブステージが!
以前ミエルカスペースに登場いただいた、GMO TECHの中原 卓馬氏が登壇。
※ブレイクタイムに行われたこともあり、本ステージはお写真だけで失礼します。ご自身の実験・実践に基づいた、非常に興味深く注目度の高い内容でした!
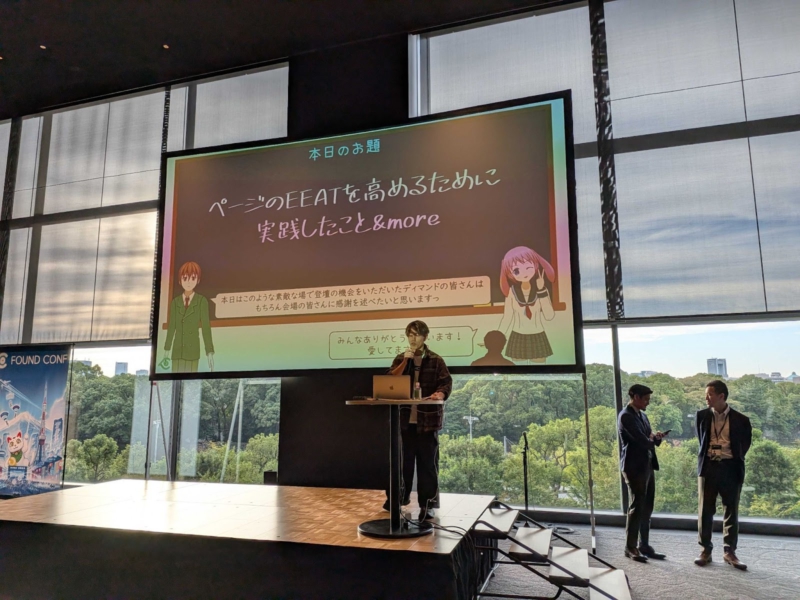
中原 卓馬
GMO TECH株式会社 執行役員
大学卒業後、約10年間証券業界でセールス・運用コンサルタントとして活躍する。その後、IT業界に転身し不動産関連の比較サイト運営企業でWEBマーケティング戦略、制作ディレクション、運用改善、セールスコーチングなどを担当し、デジタルマーケティングの知見を深める。2012年に株式会社サムライファクトリーに入社し、事業本部長としてサービス開発や組織づくりを牽引。2015年には同社の事業部をCROCO株式会社として分社化し、取締役COOに就任。2025年にGMO TECH株式会社に執行役員としてジョイン。多岐にわたる豊富なキャリアと実績を武器に、マーケターおよび事業統括者として組織運営やグロースに奔走している。
(引用:ページのEEATを高める方法について – FOUND Conf)
セッション⑦ AIで激変する検索結果にSEOと検索広告トータルでどう立ち向かうべきか?
休憩の後は、アユダンテの江沢 真紀氏、杓谷 匠氏が、SEOだけではなく検索広告も含めたセッションを展開。

江沢 真紀(写真左)
アユダンテ株式会社 SEOコンサルタント
アユダンテの創業メンバー。SEOは2001年から、数百のプロジェクトに携わる。書籍「いちばんやさしい新しいSEOの教本」などを執筆、セミナー登壇も多数あり。
杓谷 匠(写真右)
アユダンテ株式会社 デジタルストラテジーディレクター
2008年にグーグル株式会社に広告営業職の新卒一期生として入社して以来広告主・広告代理店・広告プラットフォームなど様々な立場で15年以上Google広告を中心にデジタルマーケティングの営業、運用、分析業務に携わる。2019年に英国に本籍を置く広告代理店Jellyfishの日本法人立ち上げに参画した後、株式会社アユダンテに参画。新規ソリューションの開発に努める。
(引用:AIで激変する検索結果にSEOと検索広告トータルでどう立ち向かうべきか? by アユダンテ – FOUND Conf)
・2016年に検索広告がSEOの掲載結果を押し下げ、2024年にAI overviewsが表示、2025年にAI Modeが日本で開始
・今まで通りの個別最適では難しい
・指名検索と商品名と一般ワード、限られた予算の中で効果を最大化する必要がある
・SEOと広告を組み合わせて評価するのがおすすめ
・目標インプレッションシェア 掲載位置を指定して広告を配信することができる。AI Overviewsや競合の広告が表示されている場合に利用して掲載位置を確保することができる
・自動入札の入札価格はコンバージョン率に比例する
・目標CPAとROASを設定し獲得目的の施策と、目標インプレッションシェアで認知を目指すのが良いのではないか?
・DB型サイト(アパレル)とBtoBサイトの事例を紹介
・DB型サイトの場合、KWの数が膨大にあるので、キーワードのあたりをつけることが重要。今回の事例では、掛け合わせKWは広告においてCVレートが高かったので、SEOでも強化していくという施策に繋げられた
・また、一覧ページにおいて検索機能以外での仕様が(UX的に)いけてなかったが、改善の結果、使いやすい内部リンク構造になり各種エンゲージメントが向上した
・BtoBの事例では、SEOがそもそも全体的に未獲得だった。そもそもBtoBサイトの場合、検索結果の上位にランクインしていても、広告がその上に出ているのでCTRが取れてないケースが多い
・BtoBはキーワード、コンテンツ、UIあたりに問題があることが多い
・BtoBはキーワードの数が多くないため、サイト構造にあわせて設計することが大切
・サイト構造はAI OverviewsとAI Modeの広告にも重要
セッション⑧ 乱気流を飛びこなす:LLM時代のフライトプラン
さあ、セッションもラストスパートです!Noah Learner(ノア・ラーナー)氏が、LLMにフォーカスしたセッションを展開。
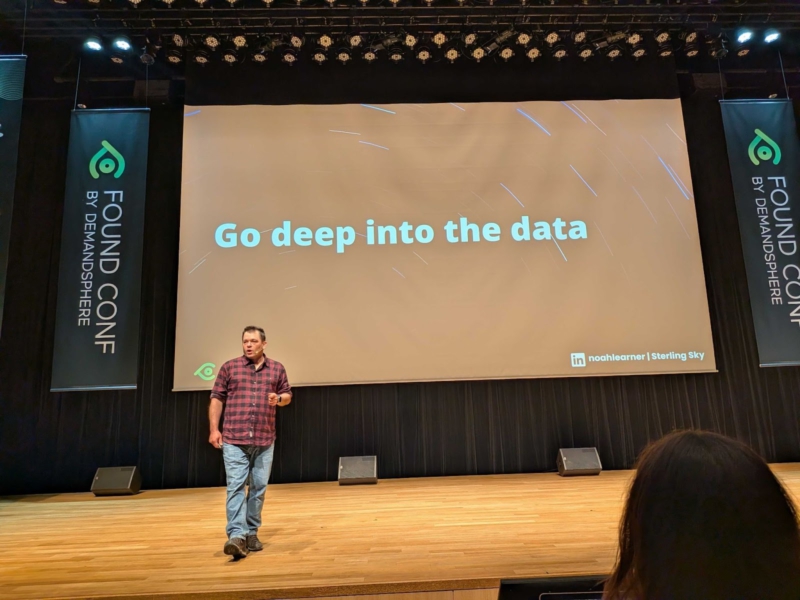
ノア・ラーナー
Director of Innovation, Sterling Sky
2001年からデジタル業界に携わり、最先端のSEOツールやレポーティングシステム、自動化ソリューションを開発してきました。業務効率化のプロとして、数多くのクライアントでROI向上を実現してきた実績があります。粘り強い問題解決力を強みとし、収益につながるチャンスに果敢に挑む姿勢で知られています。これまでに MozCon、SearchLove、brightonSEO、LocalU などの国際的なSEOカンファレンスに登壇し、多数のポッドキャストにもゲストとして出演。さらに、世界中から4,000人以上の検索マーケターが参加している「The SEO Community.com」を立ち上げた創設者でもあります。プライベートでは家族とのキャンプを楽しみ、愛犬のシャドウとマックスとの散歩や、フライフィッシング、コロラドの大自然でのスキーを満喫しています。
(引用:SEO乱気流を飛びこなす:LLM時代のフライトプラン by ノア・ラーナー- FOUND Conf)
・クライアントがどの様に収益を得ているかを考えないといけない
・我々はオーガニックに注目しがちだが、Google以外にも様々なチャネル(例えばYouTube)からの収益があるはず。GA4を利用して、それぞれのチャネルからのデータを取得しモニタリングすることが重要
・Source、Medium、Campaingなどがあるが、AI検索はこうしたチャネルの中にはない。Organic Searchにフィルタリングされてしまっているため、カスタムで設定しておく必要がある
・AI検索も含め、データの分析は、週ごと、日ごとというように粒度を変えてでモニタリングしていくことが必要
・一言にAI流入と言っても、ランディングページ、イベントの有無でフィルタリングするなど様々な手法がある
・オーガニックのトラフィックは落ちているので、CVRや平均単価、1リードの価値を高めなければいけない。が、我々はそこに対して積極的に行動しているだろうか?
・マーケティングの予算をオーディエンスがいるところに投下できているだろうか?あなたのカスタマーのことをどれだけ理解できているだろうか?
・異なる粒度で、より広く、より狭いタイムラインでデータを見ることが大切。週ごと、日毎で見てみると、違う見方が出てくる
・課題に向きあうとき、疑ってかからなかったり、他のものと一緒に考えなかったり、可能な限り深く掘り下げなかったりするとうまくいかない。情報を収集する方法を学ぶことで、その情報から洞察を得て、テストを実行し、結果を見て、トラッキングし、継続的に改善していくことができるようになる
・当たり前をなくしてみる(バイアスをなくす)ことが重要
・実施が容易でインパクトが大きいことから優先して行う
Closing Keynote
最後はみなさんお待ちかね、Rand Fishkin(ランド・フィッシュキン)氏によるセッションです!!

ランド・フィッシュキン
Cofounder of SparkToro & Snackbar Studio
SparkToroの共同創業者兼CEOであり、インディーゲーム開発会社Snackbar Studioの共同創業者。執筆、動画、講演、そして著書『Lost and Founder』を通じて、人々がより良いマーケティングを実現することを目指している。仕事をしていないときは、最愛のパートナーであり作家のジェラルディン・デ・ルイターのために手の込んだ料理を作っていることが多い。MozおよびInbound.orgの共同創業者でもあり、『The Art of SEO』の共著者。これまでに世界中で100回以上、マーケティング、テクノロジー、スタートアップ関連のイベントで基調講演を行っている。
(参照:Rand Fishkin’s Bio, Speaker Rates, Contact Details | SparkToro、翻訳は筆者)
・テーマはトラフィックの終焉とアテンションの成長について。基本的には北米とヨーロッパのデータに基づいてセッションを展開
・1990年代~2015年まではGoogle、Facebookなどの急速な成長に引っ張られ、特にマネタイズしなくとも収益化ができていた
・現在ではアメリカのデスクトップユーザーのプラットフォームの推移はそんなに変わっていない。各種SNSも鈍化
・AIプラットフォーム(ChatGPT、Geminiなど)は成長しているが相対的なシェアは小さく、伝統的な検索(Google、Bingなど)のシェアは奪っていない
・AIプラットフォームの成長率が低下傾向にある。ヨーロッパは北米とくらべると成長率は高い。日本も北米よりは高いがヨーロッパよりは低い
・ユーザー成長の限界に伴い成長転換がおきている
・例としてFacebookの平均エンゲージメント率はピークに比べて劇的な低下をみせている(99%減)
・各種SNSはプラットフォーム外へのリンクを嫌っていて(Facebook、X、Linkdin)プラットフォーム内の滞在時間に重点をおいているアルゴリズム
・結果、SNSから他メディアへの参照トラフィックは減少傾向
・Googleは利用者(検索数)は2016年から伸ばし続けているがゼロクリックの割合は高くなっていて、参照トラフィックも減らしている
・AIプラットフォームも外部へのトラフィックをほとんど送信しない
・いまだメディアへのトラフィックは検索(Google)が圧倒的だが、一部の企業に集中してしまっている傾向にある
・シェアではなく時間の使い方に目を向けるとSNS、ニュース、ECなどに時間を費やしていて、検索は時間消費のカテゴリだと5番目
・インターネット上でのアテンション(注目)は増加している
・トラフィックから影響力へ最適化を変更する必要があるかも?
・ブランドの存在を借りた土地(Webサイト外)に拡大させる
・ターゲットユーザーが時間を費やす場所(Reddit、Podcast、SNS、ニュース)を特定する
・ゼロクリックでも成功した事例を紹介。超音波ナイフのYouTubeでは概要欄などにあえてリンクを設置しなかったが、間接的にサイトに訪れて50万ドルの売り上げを達成。指名検索以外の参照トラフィックはほぼゼロ
・トレンドを追うのではなく、オーディエンスに影響を与えられるものに対してフォーカスをすることが必要
最後にレイさんから挨拶があり、2日間にわたるカンファレンスが終了しました!!!
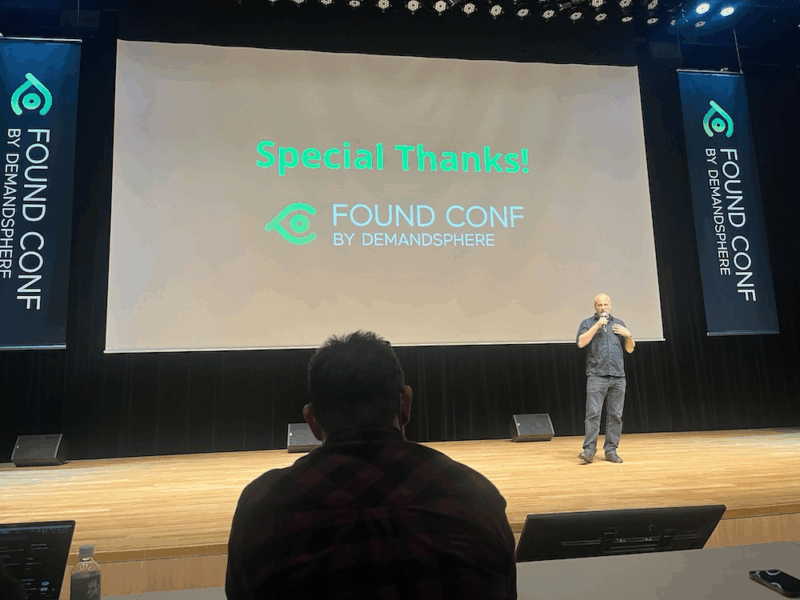
2日間の総括
これほどまでにグローバルなカンファレンスは、日本では間違いなく初めてだったと思います。
実際、日本ではこれまであまり語られてこなかったテーマのセッションも多く、AIひとつをとっても、さまざまな視点や立場からの意見を聞くことができ、とても刺激的でした。
一方で、日本ならではのデータや事例、リアルなエピソードも数多く紹介され、学びが深まる場でもありました。
SEOに携わる一人として、これからも日本のSEO業界をさらに盛り上げていけるよう努力していきたいと思います。
素晴らしいイベントを企画・運営してくださったDemandMarketsの皆さま、スタッフの皆さま、本当にありがとうございました!!!
【おまけ】
渋谷のMIYASHITA PARKで行われたアフターパーティーでは、Lily Ray氏がDJを、Mike King氏がラップを披露。最後まで大盛り上がりでした!
#SEO #FOUNDConferenceTokyo2025 #検索エンジン最適化






 この記事をシェア
この記事をシェア