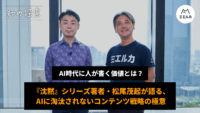様々な領域の「知」を求めて、有識者の皆さんと対談する連載「 #知の探索 」。インタビュアーは当社執行役員の月岡克博が務めます。
今回のゲストは、株式会社FRDジャパン CEO 十河哲朗さんです。千葉県木更津にあるFRDジャパンのプラントでは、世界中で需要が増え続けているサーモンの陸上養殖が行われています。
「おかそだちサーモン®」と名付けられた国産生サーモンは、首都圏にて販売を開始。2023年7月には210億円を調達して、国内最大規模のサーモン陸上養殖場の建設がスタートしています。「陸上養殖という点において、サーモンほど将来性のある魚を知らない」と語る十河さん。それほどまでにサーモンに可能性を感じた理由や、事業を立ち上げてからの苦労などを伺いました。
(執筆・撮影:サトートモロー 進行・編集:月岡克博)
DNAレベルで刻み込まれていた魚好き
月岡:
まずは、十河さんはどのような子供時代を過ごしたのか教えてください。幼い頃から魚が好きだったのでしょうか?
十河:
そうですね。私は関西の出身で、小さい頃から魚を釣ったり飼育したりする毎日を過ごしていました。小学一年生のころは、近所でザリガニをよく捕まえていたかな。その頃から生き物が好きで、その中でも特に魚が好きという感じでした。
月岡:
なぜそこまで魚にハマったのでしょう?
十河:
魚が一番好きとはハッキリ言えるんですが、理由を聞かれると……結構悩みますね。そうなってしまうくらい、そういう存在として生まれたというレベルで魚が好きなんですよね。
「なぜ日の出がキレイだと思うの?」と聞かれても、論理的な説明って難しくないですか?きっと合理的な理由はあるんでしょうが、ほとんど本能的に人は”日の出を美しい”と感じていると思うんですよね。
あえて語るとするのならば、千差万別に存在する魚が、それぞれどのように進化したのかを考えるのが好きなのかなと。私は北海道のイトウ釣りが一番好きなんですが、春になると、イトウの餌となる魚が川上に遡上してきて、それにつられてイトウも上流へ現れる。その一連の生態系に思いを馳せるのが楽しいんです。
……とまあ、魚の魅力自体はいくらでも語れるんですが、あまりに好きな要素が多すぎてなかなか説明が大変で。なので、普段は魚の面白さを説明するということ自体を、ほとんど放棄しています(笑)。魅力を口にすればするほど、むしろその言葉が安っぽくなってしまう気すらしています。

月岡:
言葉にするものではないと。その発言だけでも、十分に十河さんの“魚愛”が伝わってきます。
魚類学者を目指すも、商社に就職
月岡:
魚好きな十河さんは、その後どのような学生時代を経て大人になっていったのですか?
十河:
基本的に、生活の優先順位の一番上に”魚”がある毎日を送っていました。高校時代は自転車で、大学生になってからは原付きバイクで、時間を見つけては魚釣りに出かけていました。
将来は魚類学者を目指そうと思い、京都大学の農学部に進学しました。ただ「好きなことばかりを追い求めても、現実的にはそれが仕事になるとは限らないよな」と思うようになったんですよね。
それで三井物産に就職しました。「金属資源本部」という部門に配属され、クロムというレアメタルの輸入販売事業やオーストラリアの鉄鉱石事業などに関わりました。
月岡:
魚とはだいぶ離れた領域で働き始めたのですね。
十河:
魚と同様に自然が好きで、漠然と「自然環境に関わる仕事に携わりたい」という気持ちがありました。当時はリサイクル、特にプラスチックや金属資源の再利用などが注目されていたんですよね。これらの資源を扱う事業に携わりたいと思ったのが、就職先を決めた主な理由です。
約6年間、この部門で仕事をしていて充実感も味わえました。ですが「やっぱり魚に関わる仕事をしたい」という気持ちが大きくなっていきました。
そんなとき、三井物産の中で水産チームを拡充するという話を耳にしたんです。私は真っ先に手を上げて、そこからグループ会社の三井物産シーフーズに出向し、水産物の輸入販売事業に関わるようになりました。
そこでは、世界中を回っておいしい魚を買い付けてくるという、夢のような仕事ができました(笑)。魚に関する愛と知識量は、ほかの商品と比較すれば圧倒的に大きいこともあり、仕事もうまくいきやすいし、とにかく楽しい日々でした。好きなことを仕事にするのは本当に幸せなことだなと、そこで痛感しました。
そうして「水産業界は楽しい!」と思いながら仕事をしていた2015年に、FRDの創業者である辻洋一、小泉嘉一の二人に出会うわけです。
FRDとの出会い、サーモンの価値
月岡:
お二人との出会いにはどのような経緯があったのですか?

十河:
商社には日々、さまざまな会社様からの相談が舞い込んできます。そのうちのひとつに、ある自治体から「地元の名物海産品であるアワビを陸上養殖できないか」というものがありました。
今日、日本では漁獲量が増えすぎた影響で、どの漁場でも魚がなかなか穫れなくなっています。それはその自治体さんにとってはアワビだったようで、しかも漁業の担い手も不足している。地元の名産であるアワビを絶やさない方法として、その自治体は陸上養殖という手段に目をつけたわけです。
こうした相談を受けた場合には、自分の勉強にもなるので、調査をして相談者と事業者をつなぐようにしていました。このときも、陸上養殖を積極的に行っている事業者や技術者を調べていたところ、辻と小泉の存在を知り、彼らが運営している埼玉県の養殖場に足を運んだんです。
そこで、陸上養殖の難しさや二人が開発した「ろ過装置」のことを学ぶうちに、この技術をほかにも活かせないかと思うようになりました。そこで思い至ったのが「サーモンの陸上養殖」だったんです。
月岡:
なぜサーモンだったのでしょうか?
十河:
このとき、私はちょうどサーモンの輸入を担当していました。皆さんもご存知だと思いますが、サーモンは現在、日本のみならず世界中の需要が爆発的に伸びていて、供給量が足りないんです。
これは人口増加という要因もありますが、一番の理由は食文化の成熟が挙げられます。
近年、魚は優秀なタンパク源として注目を浴びています。タンパク質の供給源は牛、豚、鶏、魚、大豆と限られている中、牛や豚は飼育の過程で温室効果ガスを排出する点や、土地・水を大量に使用する点が制限となっています。鶏にしても、飼育には広大な土地と大量の飼料・水分が必要です。
その点、魚は土地も水分も不要で、飼料の効率も非常にいい。栄養価も高く、フードテックの文脈では「タンパク源は魚しかない」と語られることもしばしば。都市化が進むほど、魚の需要が伸びるという状況が続いているんです。
魚の中でも、特にサーモンの需要が伸びているのは、何と言ってもその美味しさにあります。それに、サーモン独特のオレンジの身というのは、他の魚では代替できないんです。白身魚の場合、ブリやタイの需要が伸びて価格が上がるにつれて、スズキなど別の魚に代替されることがあります。
月岡:
サーモンはそうした代替ができないと。
十河:
そう。約40年前までは、天然の魚の漁獲量だけでも十分に需要と供給のバランスが取れていました。しかし現在、養殖と天然は1:1のバランスにまで肉薄しています。そのなかで、サーモンについては供給力不足が顕著です。
月岡:
同じく需要の高い魚といえば、マグロも海外の方にも人気ですし、養殖のニーズは高そうに感じます。
十河:
サーモンは養殖適地が限られていることが課題ですが、マグロの場合は人工種苗生産の難しさが課題です。いわゆる完全養殖が確立されていないので、天然の種苗を使う必要があり、生産増の課題となっています。つまり、陸上養殖が課題の打ち手となっているかというと、必ずしもそうではないんですよね。
その点、サーモンは人工種苗生産という観点での難易度は高くありません。一方で、とにかくサーモン養殖は”場所を選ぶ”というのが課題です。一年中18度以下の冷たい海水と、波風を防ぐことが可能なフィヨルド地形が必要で、これらを兼ね備えるノルウェー・チリに生産が偏っています。
しかし、すでに両国ともに海面養殖適地にはイケスがひしめき合っており、生産拡大余力は大きくありません。そこで、サーモンを海に依存せずに生産する陸上養殖が必要になってるわけです。「大きな需要があるけれど、養殖適地が限られている」という点が、サーモンが陸上養殖にうってつけな理由です。
辻と小泉は、ろ過設備自体の販売を事業展開しようとしていました。私はそんな彼らに「その装置を使ってサーモンを養殖してみませんか」と提案しました。その後、サーモンの陸上養殖を事業とする会社を設立し、三井物産の人間として9億円を出資しました。それが2017年のことです。
その後しばらくして「この事業は自分の残りの人生をかけて成功させる価値のあるものだ」と思い、三井物産を辞めて事業に参画しました。

12回連続の失敗、ブレイクスルーのキッカケ
月岡:
さまざまな想いからFRDに十河さんも参画したのですね。実際に事業をスタートさせて、どのような苦労がありましたか?
十河:
一番の苦労は、スケールアップでした。三井物産による出資の前、FRDがアワビの養殖をしている水槽のひとつを使ってサーモンの養殖をやってみました。水槽の大きさは1.5トン程度で、ちょうど私たちの目の前にあるテーブルくらいの大きさです。
月岡:
サーモンは通常、どれくらいまで育てたら出荷できるようになるのですか?
十河:
自然界の場合、成魚になるまで4〜5年を費やす必要がありますが、既存の海洋養殖であれば約2年くらいが一般的でしょうか。最初にアワビ水槽でサーモン養殖を行った際には、1年半で出荷サイズまで成長させることができました。これはいけるな、と三人とも感じていましたね。
出資後に現在の木更津の施設が完成し、大規模なプラントでもこの成長速度を再現できるのか早速試しました。しかし、成長も思ったようにしないし、死んでしまう個体もぽろぽろ出続ける状態でした。
月岡:
埼玉の成功体験を再現できなかったのですね。
十河:
小規模でできたことが再現できないのはなぜなのか、生育環境を変えてトライしてもうまくいかない。12世代連続で失敗し続けるという状況で、2年経過してしまいました。3年目には「これ以上ミスを重ねれば、会社をたたまないといけないかもしれない」という苦境にまで追い込まれていたんです。
「魚が育たない」という現象は、なにか大きな問題がひとつあるというよりも、複合的な要因が折り重なって生まれます。そこで私たちは、これまで10パターン程度だった水質の変更点を数十パターンまで増やし、あらゆる条件を検証し直しました。ゼロベースで水質の条件をベストだと考えられるポイントに設定しました。
その結果、13世代目にようやくブレイクスルーを起こすことができ、1年半で3kg程度の大きさまで成長させることができました。現在は33世代目のサーモンを育成中ですが、約1年で出荷可能なサイズまで育てられています。
業界でも「ベストで2年」とされるところ、半分の期間に短縮できるだけの「黄金律」を試行錯誤の末に私たちは発見できたんです。

月岡:
ものすごい進歩ですね。
十河:
サーモンの陸上養殖には設備も非常に重要で、FRDはそこにも自信があります。ここに、これまでに培ってきた養殖のノウハウが組み合わさってはじめて、魚が健やかに育つんです。
木更津のプラントでは、もともと「年間30トンのサーモンを出荷する」ことを目標としてきましたが、設立から6年をかけた2023年に約35トンの出荷に成功しました。そして昨年7月、私たちは210億円の資金を調達して、いよいよ商業規模のサーモンの養殖プラントの設立に乗り出しました。そこでの目標は「年間3,500トンのサーモンを出荷する」です。
月岡:
今の100倍ですか。ロマンがありますね……!
陸上養殖技術を日本から世界中へ、FRDのこれから
月岡:
新たなプラントの設立も含めて、これから十河さんとFRDが目指す先を教えてください。
十河:
まずは、日本でさらに大きなプラントを作り、サーモンの出荷量を拡大していきたいですね。世界における養殖サーモン類の生産量は約400万トン、そのうち日本では約20万トンが消費されています。今度建てられるプラントで3,500トンを生産しても、日本の養殖サーモン需要から見ると1-2%にしかなりません。なので、その先にはさらに大型のプラントへの拡張も計画しています。
先ほど申し上げた通り、世界の生産量のうち、約80%がノルウェーとチリの海洋養殖に依存していますが、両国での生産量は限界が近いと言われています。
月岡:
なぜでしょうか?
十河:
海への環境負荷や、天然魚への影響等を理由として、両国政府が養殖ライセンスの追加発行を制限しているからです。
一方で、世界中のサーモンの需要はまだまだ伸び続けるでしょう。そこで重要となるのは、陸上養殖により、需要がある場所でどこでもサーモンを生産できるようにすること。私たちは日本だけでなく、海外にもサーモン陸上養殖の生産拠点を作れるようになりたいと考えています。

月岡:
日本で育てたサーモンを世界に輸出するのではなく、需要の多い場所にプラントを作ってしまうと。
十河:
そうです。サーモンは鮮度の都合上、飛行機による輸送が必要です。しかもノルウェー・チリという北極・南極に近い場所から運ばれるため、決して安くない輸送コストがかかります。これは日本から輸送するという点でも同様です。
サーモンを必要とする現地で陸上養殖できれば、輸送コストが大きく下がります。
月岡:
サーモン陸上養殖には、社会課題を解決しつつ、きちんと経済的な合理性まであるのですね。世界中にFRDのプラントができるのが今から楽しみですね。
最後に、十河さんが仕事で大切にしていることや、若い世代にアドバイスしたいことを教えていただけますか。
十河:
そうですね……。たまにこうした質問をされるんですが、正直パッと出てこないんです。ひとつ言えるとすれば「好きなことをただやるだけではダメ」ということでしょうか。
月岡:
十河さんはむしろ、好きなことを追究して今の道を見つけた人という印象でしたので、その言葉は意外です。
十河:
私は社会人として最初の6年間、鉄鉱石事業などで数字を常に追い求めていました。今でこそ好きなことに関する仕事をしていますが、そのなかでも「もっとも数字が出る勝ち筋を常に見極める」という点は大切にしています。
魚や宇宙といった産業は、いわゆるマニア的な視点になりがちです。それは決して悪いことではありませんが、数字を度外視してワクワクだけを追い求めると、そもそも成功する可能性が高くない座組でビジネスを始めることにもなってしまいかねません。
「サーモン陸上養殖」は10年20年先に水産業界の一角を担う分野になるという確信があるからこそ、私はこの事業に人生をかけています。その算段がなければ、今でも水産物の輸入販売を楽しく続けていたと思います。
「好きなことをやろう」という言葉は非常に甘美だからこそ、数字や勝ち筋という観点を忘れないこと。それを抜きに若い方々の背中を押すのは、彼らの幸せにはつながらない場合もあるなと思っています。
月岡:
弊社の創業者である古澤暢央も「ロマンとそろばん」とよく言ってます。好きと数字の両方を大切にしたからこそ、十河さんは大きな挑戦ができているのですね。十河さんの壮大なチャレンジを応援しています!
<FRDジャパンでは一緒に働く仲間を募集中!募集職種はこちらから>







 この記事をシェア
この記事をシェア